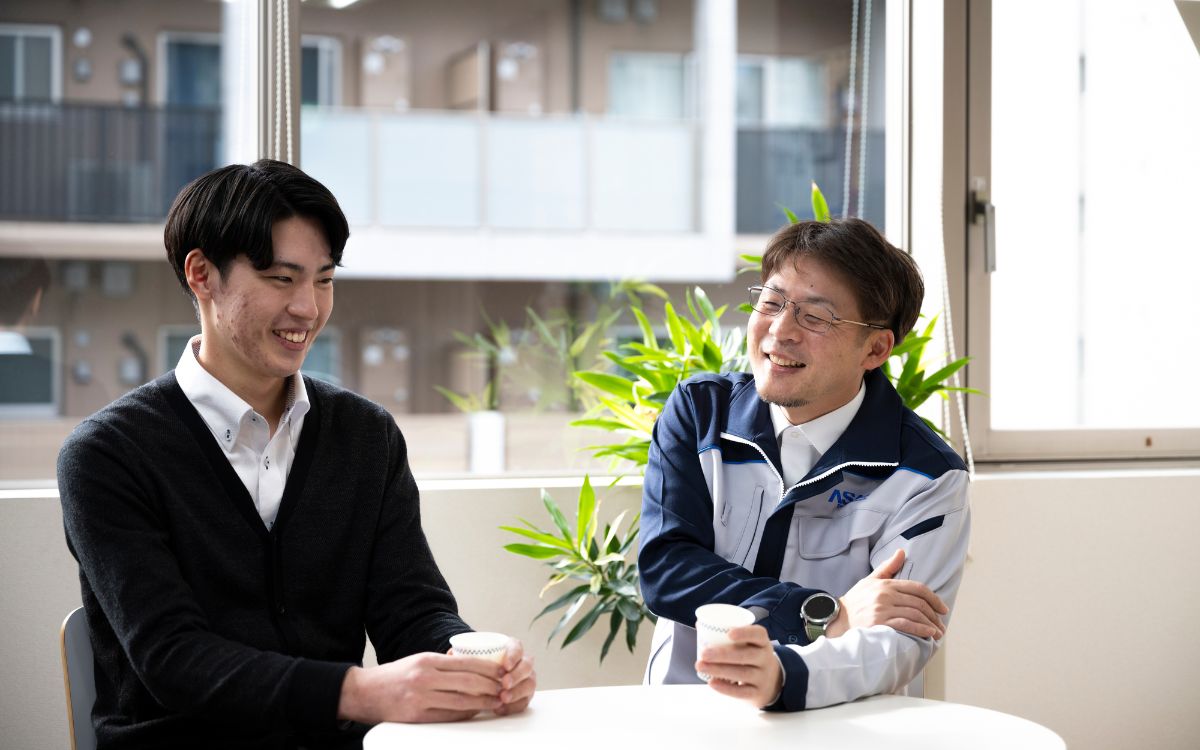プロとしての責任感×明るい社風。電気の技術やスキルを極めていくには最適なフィールドだと実感
プロとしての責任感×明るい社風。
電気の技術やスキルを極めていくには最適なフィールドだと実感
このストーリーのポイント
- 仕事を楽しんでいない先輩の姿を見て、転職を決意
- アットホームな社風と尊敬できる方の存在に惹かれ浅海電気に入社
- 数年に及ぶ大規模な現場を次々と担当し、有意義な経験を積み重ねる
電気工事の総合企業である浅海電気。関西国際空港や東京ミッドタウンなど大都市のランドマーク的な建物の案件を多数手がけている。いずれの現場も施工管理のプロと呼ばれる人材らがチームを組み、お互いに助け合いながら業務に取り組んでいる。中途で入社してきた矢持も、働きやすさを存分に堪能している。今後は、若手の育成にもより注力していきたいと考えている。
浅海電気株式会社
K・Y
大阪本店工事第一部工事課
2013年中途入社
電気デジタル情報科卒

芸術系大学を卒業後、電気を学ぶために専門学校へと進んだ。新卒で入社した会社は、想像とは違った職場環境。将来のことを考え、転職することを選んだ。回り道をしてきたように思われるかもしれないが、その場その場で常に全力投球してきたからこそ今があると信じている。浅海電気に入社してからは、公私ともにますます充実した人生を過ごすことができているという。
手に職をと考え、電気施工管理職の道を目指す
元々、絵やインテリア、デザインなどが好きだったので芸術大学に進みました。学生生活は楽しかったですね。スノーボードのサークルに入り、シーズンになると仲間と共に滑りに行っていました。活動資金も要るので、アルバイトもかなり頑張りました。例えば、居酒屋の店員や自動車オークションの会場スタッフなどです。3年生になって就職活動の時期を迎えたのですが、自分に合う仕事がなかなか見つかりませんでした。それで、「手に職を得るしかない」と考え、専門学校に入り直し電気を学ぶことにしたんです。
専門学校では2年生になるとすぐ就職活動に入ります。「電気に関わる仕事をしたい」と決めていました。もうこれ以上、遠回りするわけにはいきません。「まともに就職しよう」と考えたからです。それで入社したのが、関西一円をカバーする電気工事の総合企業でした。僕の地元・兵庫県の会社ですし、専門学校の先生も熱心に勧めてくれていました。
職種は電気施工管理職。主に現場で作業する技術者を監督したり、作業の指揮をするなど、現場での電気に関するすべてを管理する仕事です。実際に働き始めてみたところ、とにかくハードワークでした。残業時間がかなりあったんです。それに誰もが仕事に追い詰められているので、現場はいつもピリピリしていました。冗談も言えない、そんな雰囲気でしたね。唯一の救いは、給料が良かったことぐらいです。先輩らを見ても仕事を楽しんでいる様子が全く伝わってきませんでした。将来を見据えたときに、こういう先輩にはなりたくないと考えたのが、転職のきっかけでした。それでも、自分が担当していた工事現場を中途半端な状態で放り出したくはなかったので、やり切ったところで辞めることにしました。結局、そこには2年間在籍しました。
ただ、退職してからもこの仕事は続けたかったので一旦は派遣会社に登録し、幾つかの現場に入っていました。実は、当社の存在を知ったのはそのときでした。当社の案件に派遣雇用という格好で半年間ほど参画することになったんです。なので、当社の方々と会話を交わす機会が多々ありました。その流れの中で、「うちで働いてみないか」と幹部の方に声を掛けてもらえたんです。その方は、いつも心に余裕があり、穏やかな印象でとても尊敬していました。こういった方が在籍される会社であるなら、働きやすいでしょうし、仕事内容も前職と変わらなかったので「経験を活かせるはずだ」と考え、入社することを決めました。

裁判所の改修を初めて担当。先輩らに支えられながらもやり切る
入社後は主に電気工事の現場代理人という立場でさまざまな案件に関わらせてもらっています。現場代理人とは、大規模な建物の電気工事の責任者として現場全体を管理するポジションです。具体的には、予算管理や工程管理、品質管理、安全管理などを担います。既に、1社目で現場代理人としての経験が1年近くあったので、会社としても「任せても大丈夫だ」と判断してくれたのかもしれません。
自分自身でも、問題なく対応できる自信があったのですが、最初はそう簡単にはいきませんでした。担当したのは、大阪高等裁判所の改修プロジェクト。これが予想外に大変でした。何しろ、オフィス施設や文教施設などに従事したことはあったものの、裁判所は初めてです。これまでに関わったことがない人たちと仕事でやりとりすることに当初は戸惑ってしまいました。しかも、平日は裁判が行われています。そうした中で電気工事を行い、もし電気のトラブルや停電が起きたりしてしまうと、ニュースとして取り上げられてしまいます。なので、結構気を遣いました。
まずは、とにかく建物を理解するしかありません。どういうシステムで構成されているのかを理解した上で、どんな工事を進めていくか、どこの範囲であれば電気系統を切り離しても問題がないかとロジックを立てて工事を段取っていきました。
有難かったのは、先輩方のサポートです。裁判所の案件は停電工事ができる土曜・日曜がメインだったのですが、先輩方は休日でありながらも顔を出してくれたり、工事の応援に来てくれました。官庁に提出する書類のサンプルを持ってきていただけたこともあり、本当に助かりました。おかげで1年後に無事やり遂げることができたときは、さすがに嬉しかったです。

さまざまな現場に携わり、電気の奥深さを知る
その後は、兵庫県尼崎市にある地方裁判所の新設工事に現場代理人として2年間入り、次に山口県内の国立大学の新築工事を2年ほど支援しました。こちらは現場代理人ではなく、一担当者という立場であったので、自由に仕事をさせていただけました。
それが落ち着いた後に、再び大阪高等裁判所の耐震改修工事に現場代理人として関わりました。第1期工事が3年。続いて第2期工事も3年と延べ6年にも及ぶロング・プロジェクトでした。耐震改修工事では、耐震ブレースや耐震壁等の構築に関わる電気改修。また、裁判所内全ての照明改修や裁判所独自の警報システムも一新しました。現在は、また別の裁判所の受変電工事に現場代理人として携わっています。今まさに、進行形です。
いずれの現場でも、そして本社であっても共通して実感したのは、アットホームな職場であることです。全社的に居心地が良いですね。その点は常に感じています。なので、他の部署の皆さんとも仲良くさせてもらっています。
また、働きやすさを実感できるのも当社ならではです。会社が気を遣って、有給の取得や育児休暇もすすめてくれます。
もう一点、電気工事の総合企業としての地位を確立している点も当社の魅力としてアピールしたいです。元請け業者であるゼネコン(ゼネラル・コンストラクターの略称)さんから絶大な信頼が寄せられています。
多くの人は、ゼネコンさんに言われるがままの仕事をしているのではないかと思っているかもしれませんが、それでは、ゼネコンさんから必要とされなくなりますし、認めてもらえません。だからこそ、僕自身はゼネコンさんとのコミュニケーションを大切にしています。建物を作る仕事とはいえ、作るのは人です。当然ながら、何かをお願いされたら快く引き受けますし、ゼネコンさんの期待を上回る仕上りが実現できるよう取り組んでいます。やはり、最終的には感謝されて、次の仕事に繋げたいですからね。それは、僕のこだわりかもしれません。
おかげで、当社に入社してから電気施工管理として少しは成長できた気もしています。電気施工管理技士1級も取得しました。ただ、正直言えばまだまだです。学ばなければいけないことが沢山あります。電気は奥深いですからね。それでも、当社であれば免許や資格取得に向けた社内講習が充実しており、スキルアップには最適なので電気を極めていくには最適だと思います。案件が多様ですし、大規模なプロジェクトも次々と立ち上がっています。それに、資格取得へのサポートや社員同士のナレッジシェアも活発だからです。

制約がほぼないので、モチベーション高く働ける
僕も今年で40代になります。今後は、自分のためだけではなく、後輩たちのためとか、会社のためにどんな支援ができるかを考え行動していく必要があると思っています。特に若手の面倒を見るのは、大変であるものの喜びも大きいです。意欲に溢れる子たちが多いので、その想いに応えてあげたいというのが、僕の今後の目標です。肩書にはあまりこだわっていません。むしろ、ずっと現場に携わっていきたいです。楽しいですからね、現場は。当社に来てから、それをより一層実感しています。
気づいたら、当社に入社してもう10年が経過しましたが、本当に入って良かったと思っています。何しろ、仕事を進めるに当たって自由度が高いので、現場では自分の意見やアイデアを発揮していけます。それだけに、いつもモチベーション高く働けます。皆さんもきっとそう感じてもらえるはずです。いつの日か、同じ現場で働くことができたらと願っています。