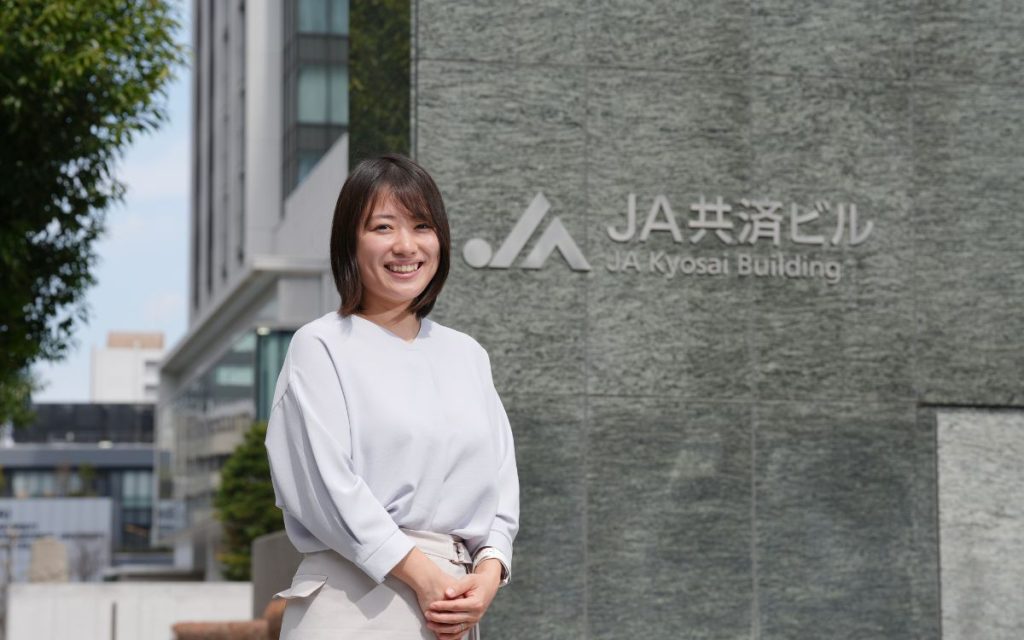「一日でも早く共済金をお支払いする」――若手職員が能登半島地震の最前線で挑んだ、共済の使命と助け合いの精神
「一日でも早く共済金をお支払いする」――若手職員が能登半島地震の最前線で挑んだ、共済の使命と助け合いの精神
このストーリーのポイント
- 未曽有の災害である能登半島地震の被災地で、共済金支払いという重要な使命を担う
- 不安と戸惑いを抱えての現地入り。契約者の方々の優しさや仲間の協力に支えられる
- 非営利団体であるからこそ、有事の際に他の保険会社とは異なる存在意義を発揮できる
未曽有の被害をもたらした2024年1月1日の能登半島地震において、JA共済連は、地震共済金のお支払いという重要な使命を果たすため、迅速に災害対応を開始しました。その最前線で奮闘したのが、建物共済グループに所属する山口と國方という二名の若手職員です。入会間もないながらも被災地での損害調査業務を任された二人が、現地の対応を通じて何を感じ、どのように成長を遂げたのか。二人の対談を通して、有事におけるJA共済連の存在意義、そして「相互扶助」の理念に基づいた助け合いの精神がいかに重要であるかが明らかになります。非営利団体であるJA共済連が、有事において他の保険会社とは異なる存在意義を発揮する様子も垣間見えます。
JA共済連(全国共済農業協同組合連合会 全国本部)
山口 侑希
業務部 建物共済グループ
2023年入会 経済学部卒

「もしものときに誰かを支えられたら、やりがいに繋がるのでは」。その想いが強かっただけに、就活では保険会社を中心に見ていた。中でも、JA共済連を選んだ最大の理由は、職員の方々の温かい人柄に惹かれたから。新入職員として能登半島地震の被災地に損害調査に携わったときには、まさにその二つを体感したと語る。現在は、損害調査に関する研修会の企画・運営や、最新技術を活用した落雷事案の自動査定に関する企画業務を担当している。
國方 颯人
業務部 建物共済グループ
2022年入会 経済学部卒

「人の生活を身近で支えたい」という強い思いからJA共済連に入会。入会後の研修で建物に対する保障の重要性を知り、その支払いを統括する建物共済グループへの配属を希望する。現在は、災害調査で使用するタブレット端末「Lablet’s」内のアプリ改善や、携帯用の調査アプリ開発などを主に担当。平時はデスクワーク中心であるが、ひとたび災害が発生すると、被災地での重要な任務に対応し、最前線で契約者の方々の生活を支えるという、非常にやりがいのある仕事だと語る。
共済金の支払いを通じて、契約者の生活を支える仕事だと実感
―JA共済連への入会の決め手や組織に対する想いからお聞かせください。
山口 私がJA共済連に惹かれたきっかけは、「相互扶助」という事業理念のもと、多くの人々の生活を支えられることに共感したからです。でも、入会の一番の決め手は、入会前に出会った職員の方々の人柄でした。職員の方々が、親身になって私の話を聞いてくださり、その穏やかで温かい雰囲気に触れて、「この方たちと一緒に働けたら、きっと充実した社会人生活を送られる」と強く感じたんです。
國方 ええ、私も山口さんと同じで、面談や座談会で出会った職員の方々の印象がすごく良かったんです。私のことを理解しようと真摯に向き合ってくれる姿勢が伝わってきて、安心感を覚えました。それに、JA共済連は事業範囲が非常に広いことも魅力でした。これから長く働く中で、自分の興味や関心が変化していく可能性もある。そんな時に、様々な分野で活躍できるフィールドがあるというのは、心強いと思いました。
山口 國方さんが実際にJA共済連で働いていて、特にやりがいや意義を感じるのはどんな時ですか?
國方 そうですね、やはり災害対応でしょうか。共済金の支払い件数や金額といった数字が、私たちの仕事の成果を明確に示してくれるからです。大変な状況に置かれた方々の生活を、少しでも早く支えられているという実感があります。山口さんはどうですか?
山口 私も、共済金の支払いに携わっている時に、まさに「契約者の皆様の生活を支える仕事」だと強く実感します。被災された方々からの感謝の声・メッセージを目にすると、この仕事を選んで本当に良かったと思えます。
―國方さんは、入会して早々に福島県沖地震の被災地に損害調査で入られたそうですね。当時の状況はいかがでしたか?
國方 入会してまだ間もない5月の末でした。発災から2カ月ほど経っていたので、現地は少し落ち着きを取り戻していた時期ではありましたが、それでもニュースで見ていた以上の被害の大きさに衝撃を受けました。そんな中でも、組合員の方々が気丈に日常を送ろうとされている姿を見て、「本当に強いなあ」と感銘を受けました。上司から「調査に行ってみるか」と声をかけていただき、迷うことなく「行きます」と答えました。入会後の研修で建物査定に興味を持っていたことも大きかったと思います。
山口 配属されてまだ1カ月くらいで、業務に慣れないことも多かったのではないでしょうか?
國方 そうですね。もちろん、当時の私はまだ自分の役割や仕事内容を十分に理解できていたわけではありませんでした。でも、「ここにいてもあまりできることがないなら、被災地に行って実際に手を動かした方が、少しでも誰かの役に立てるのではないか」と考えたんです。
山口 それはすごい決断力ですね。私だったら、初めてのことで不安でいっぱいになってしまいそうです。実際に被災地に立ってみて、特に印象に残った場面はありましたか?
國方 日頃、地域で共済の普及推進活動をされているライフアドバイザー(LA)と契約者の方々との間に、本当に深い信頼関係があることを目の当たりにしたことです。まるで家族のような親密さで、温かい繋がりを感じました。もう一点は、まさに「助け合いの精神」を肌で感じたことです。被災された方々とJAの関係性の深さを理解することができましたし、見ず知らずの私に対しても、多くの方が「遠くから来てくれてありがとう」と声をかけてくださったことが、今でも忘れられません。JAやJA共済連が長年にわたり地域に根ざし、助け合いの精神を育んできたからこそ、そのような光景が見られるのだと実感しました。

現地と東京、それぞれの拠点で能登半島地震の初動対応に追われる
―能登半島地震が発生した瞬間、お二方はどのような状況で、どのように事態を把握されたのでしょうか。
山口 まさか元旦に、あのような大地震が起こるとは夢にも思っていませんでした。その日は家族と初詣に出かけていたのですが、スマートフォンのニュース速報が鳴り響き、ただ事ではないと感じました。その後、すぐに建物共済グループ間で連絡が飛び交い、被害の甚大さを徐々に理解していったんです。ただ、その時はまだ「自分に何ができるのだろうか」「一体何から手を付ければいいのか」全く分からず、情報が少ない中で、ただ上司・先輩からの連絡を待つことしかできませんでした。
國方 私も山口さんと同じで、実家に帰省中に地震を知りました。その日のうちに、課長から今後の対応について業務指示の連絡があり、事態の深刻さを改めて認識しました。そして、明けて2日の昼過ぎには、「富山へ行ってもらうことになるから、準備をしてほしい」という電話があったんです。まさか自分がそのような重要な任務を任されるとは、想像もしていませんでした。
山口 ええ、國方さんが1月4日に出勤されたその足で富山へ向かわれたと記憶しています。確か、お誕生日だったんですよね。お一人で慣れない土地へ行かれるのは、さぞ大変だったでしょう。
國方 そうなんです(苦笑)。まさか誕生日に富山へ行くことになるとは思ってもいませんでしたが、「一刻も早く被災された方々の力になりたい」という気持ちが強かったです。富山では、能登半島地震の初動対応を統括するという重要な役割を担いました。具体的には、損害調査と査定の体制を迅速に構築し、いつまでにどれくらいの調査員が必要なのか、という対応計画を策定すること。そしてもう一つが、全国各地のJA共済連の都道府県本部から応援に来てくださる調査員の方々を受け入れるための準備です。宿泊先のホテルや移動手段となるレンタカーの手配、被災地の状況や調査の流れなどを説明するガイダンスの運営など、多岐にわたる業務を同時進行で進めていきました。
山口 國方さんが富山で奔走されていたその頃、私は東京にいました。自分に与えられた目の前の業務を、一つひとつ確実にやり遂げることに集中していました。特に、年度末に向けて校了日が迫っていた資材改訂の業務は、絶対に遅らせることはできないという強い責任感を持って取り組んでいました。それと並行して、被災地へ損害調査に行かれる方にシステム権限を付与する業務や、災害対応の事務局業務も進めていかなければなりませんでした。急に多くの業務が重なり、まさにマルチタスクの状態でしたが、何とか一つひとつ乗り越えることができました。

不安と緊張の中、被災地に立つ。そこで目にした光景とは
―國方さんが富山県本部で、まさに陣頭指揮を執られていた頃、現場ではどのような状況だったのでしょうか。まずは、國方さんが富山に入られた際のご苦労からお聞かせいただけますか。
國方 富山県は、幸いにも能登半島のような甚大な被害は受けていませんでしたが、「一体何から手を付ければ良いのか」という状況だったんです。そんな中で、東京の全国本部からの指示を仰ぎながら、私が現場で具体的に誰に何を指示するべきかを判断し、動いていく必要がありました。「誰に何を頼めば良いのか」、最初は本当に手探り状態で、戸惑いの連続でした。
山口 想像するだけでも、その場で次々と指示を出していくのは、相当なプレッシャーだったと思います。
國方 ええ。ただ、最終的な目標は東京の先輩方が明確に示してくれていたので、そこに向かって、「今、この人にこの作業をお願いしなければ」と、必死に考え、指示を出すことで、なんとか前に進むことができました。
山口 福島での被災地調査のご経験が、富山での初動対応でも活きたということですね。
國方 その通りです。福島で実際に被災地の状況を目の当たりにし、広域支援に参加した経験があったからこそ、「今、何が必要なのか」「どのような準備を進めるべきか」という具体的なイメージを持つことができました。全国各地の都道府県本部から応援に来てくれる調査員の方々の宿泊先や移動手段の手配、調査に関する説明会の準備など、福島での経験がなければ、スムーズに進められなかったと思います。
山口 本当にお疲れ様でした。お話を聞いているだけで、その大変さが伝わってきます。
國方 山口さんが、実際に石川の被災地に入られたのは、2月半ばでしたね。
山口 はい。東京での資材改訂の業務が一段落したタイミングで行かせていただきました。
國方 被災地へ行くことが決まったときは、どんな気持ちでしたか?
山口 「一日も早く被災された方々の力になりたい」と思う反面、「自分に何かできるのだろうか」と不安な気持ちでした。調査端末機「Lablet’s」の操作にも十分に慣れていなかったからです。それに、直接契約者の方とお会いすることへの緊張も、拭い切れないものでした。
國方 実際に、初めて被災地に足を踏み入れた瞬間のことは覚えていますか?どのような光景が目に飛び込んできましたか?
山口 被災地に足を踏み入れた時、言葉を失いました。ニュースなどで被害の状況は見ていましたが、実際に自分の目で見た光景は、想像を遥かに超えるものでした。胸が締め付けられるような、何とも言えない感情に包まれました。
國方 でも、実際に契約者の方々と会ってみると、気持ちに変化があったのではないでしょうか。
山口 はい。契約者の皆様の温かさに、本当に救われました。「東京からわざわざ遠くまで来てくれたんですね」「寒い中、本当にありがとうございます」と、私たちを気遣う優しい言葉をかけてくださるのです。ご自身が大変な状況にも関わらず、私たちのことを心配してくださるそのお姿に、逆に私の方が勇気づけられました。それが、何よりも印象に残っています。
國方 山口さんは、一週間ほど被災地にいらっしゃったんですよね。
山口 そうです。短い期間でしたが、最後、被災地を離れるときには、不思議なほど寂しい気持ちになりました。同時に、石川という街が、そしてそこに住む人々が、本当に温かいと感じ、大好きになりました。

「誰のために、何のために働いているのか」が明確になる
―今回の能登半島地震における災害対応を通して、JA共済連としてのチームワークと助け合いの精神について、具体的にどのような場面で感じられましたか。
山口 初めて足を踏み入れた被災地では、本当に助け合いなしでは何もできませんでした。全国各地の都道府県本部から支援に駆けつけてくださった職員の方々と協力しましたが、普段とは全く異なる環境の中でも、皆さん「被災された契約者のために、一日でも早く共済金をお届けする」という一つの明確な目標に向かって、迷うことなく行動されていました。損害調査を進める中で、分からないことがあればすぐに教え合い、支え合う。あの一週間は、まさに助け合いの連続でした。そして、富山で陣頭指揮を執られていた國方さんへの尊敬の念が、日に日に高まりました。
國方 いやあ、そんな風に言われると、照れてしまいますね。
山口 いえ、本当にそう思ったんです。発災直後、まだ状況も混沌としている中で、単身で富山へ入られ、全国から集まった損害調査員の方々と地元である富山県本部の方々の間に立ち、それぞれの要望を聞きながら、全体の調整をされていたんですよね。想像を絶する状況だったと思いますが、そんな中でも、自分が何をすべきかを冷静に判断し、的確な指示を出され、リーダーシップを発揮されていたのだと思います。今の私には、まだ到底及ばないですが、少しでも國方さんの背中を追いかけられるように、これからも努力していきたいと思っています。
國方 とんでもないです。山口さんこそ、私が富山へ行っている間、東京に残って、私が抱えていた業務を全て完璧にやり遂げてくれたおかげで、私は安心して富山での仕事に集中できたんです。本当に感謝しています。山口さんのことだから、石川に行っても、きっと被災された方々の気持ちに寄り添い、しっかりと調査を進めてくれるだろうと信じていましたし、想像していた以上に大きく成長して帰ってきてくれて、本当に嬉しかったです。
山口 今回、被災地で損害調査をさせていただいたことで、私が「一体誰のために、何のために働いているのか」という問いに対する答えが、明確になったと感じています。実際に被災された契約者の方々のお宅を訪問し、直接お話をお伺いし、家屋の損害状況を一つひとつ丁寧に確認し、一日も早く共済金をお支払いできる状態にするという一連の業務を、身をもって経験できたからです。
國方 そうですね。大変な思いをされている契約者の方々に、一刻も早く共済金をお届けし、少しでも金銭面でのご負担を軽減していただく。それこそが、私たちの最も重要な役目だと改めて感じました。
山口 災害が起こらないことが一番ですが、残念ながらそれは叶いません。だからこそ、万が一災害が発生してしまったときに、いかに迅速にお客様の生活を救済できるかが、私たちの使命だと強く感じました。
國方 ええ。地震に対する保障は、単なる物に対する保障ではなく、被災された方々が再び安心して生活を送るための、生活再建に役立つ社会インフラだと捉えています。だからこそ、一日でも早く共済金を契約者の方々にお届けすることが、私たちの使命であり、果たすべき役割なのです。そのためにも、私たちは常日頃から、いざという時のための備えを怠ってはならないと強く感じています。
山口 本当にその通りだと思います。まさに、有事の際、未曽有の困難に直面した時だからこそ、職員一人ひとりが一致団結し、組合員・利用者の皆さまのために何ができるのかを真剣に考え、行動に移していく姿勢こそが、JA共済の根底にある「相互扶助」の精神なのだと、改めて強く認識しました。

これからも地域に寄り添い、「安心と満足」を届けていきたい
―最後に、今回の能登半島地震での災害対応のご経験を踏まえ、今後のキャリア展望と、改めてJA共済連で働く魅力についてお聞かせください。
山口 今回の経験を通して、人と人とのコミュニケーションの重要性を改めて深く認識しました。そして、自分がこうして働いている意味、自分の業務が一体誰の、何のために役立っているのかが、以前にも増して明確になりました。被災された契約者の皆様に直接お会いし、感謝の言葉をいただけたことで、一日も早く、一人でも多くの方に「安心」と「満足」をお届けしたいという思いが、強く湧き上がってきました。そのためにも、日々の業務において、「いかに迅速に共済金をお支払いできるか」という点をこれまで以上に追求し、契約者の皆様、そして社会全体の安心に貢献していきたいと思っています。
國方 私が今回の対応で改めて気づかされたのは、全国本部が、各都道府県本部からいかに頼りにされているかという点です。その期待に応えていかなければならないという責任感を強く感じました。今後のキャリアとしては、もし建物共済グループで引き続き勤務させていただけるのであれば、福島県沖地震での損害調査の経験や、今回の能登半島地震で富山県本部で初動対応を統括させていただいた経験を活かして、建物査定の中心的な存在として、災害対応を指揮できるような人材に成長していきたいです。もし、他の部署に異動することになったとしても、災害が発生した際に共済がいかに重要であるかを、より多くの組合員の方々に周知していく活動に貢献したいと考えています。
山口 世の中には本当に多くの仕事がありますが、誰かの生活に寄り添い、最も不安な瞬間に手を差し伸べられる仕事こそ、何にも代えがたいやりがいを感じられるのではないでしょうか。 JA共済連は、地域に深く根付き、地域の方々に心から愛されている組織です。 その一員として、地域社会に貢献できることに、大きな誇りを持つことができます。 また、JA共済連は事業領域が非常に幅広いので、本当に多様な部署で、色々な個性を持った職員の方々が活躍されています。 そうした「人」に注目して、様々な視点からJA共済連という組織を捉えてみると、きっと新たな魅力に気づいてもらえるのではないかと思います。 私自身、入会の決め手の一つは「職員の人柄に惹かれたから」でした。 新入職員として被災地での損害調査に携わった際、まさにその優しさに支えられたと強く感じています。
國方 私は、「契約者の方が本当に困った時に、少しでも力になりたい」という強い思いを持って、JA共済連に入会しました。 地震のような災害が起きた時に、鑑定人の方だけではなく、私たち調査員が実際に契約者の方のお宅を一件一件訪問し、直接お話をお伺いして、安心をお届けする。これは、他の損害保険会社にはない、JA共済連ならではの対応だと自負しています。 その分、契約者の方々から直接感謝の声をいただける、唯一無二の環境と言えるでしょう。 もし、私たちと同じような思いを持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に働きたいと思います。 私も、入会の決め手はJA共済連が掲げる相互扶助という事業理念に共感したこと、そして「一緒に働きたいと思える人がいた」ことでした。 面談や座談会で出会った職員の方々の、自分のことを理解しようとしてくれる温かい姿勢に惹かれたんです。

——-
未来を見据え、それぞれの場所で更なる成長を誓うお二人。被災地での経験は、お二人の心に深く刻まれ、日々の業務への新たなモチベーションとなっています。地域社会への貢献、そして困っている人を支えたいという強い思い。JA共済連には、そんな熱い気持ちを持った仲間たちが集い、互いに支え合いながら、地域に「安心と満足」を届け続けています。
——-