
岡山の地で羽ばたく研究開発エンジニア。ものづくりを支える「モノづくり」に貢献。
岡山の地で羽ばたく研究開発エンジニア。
ものづくりを支える「モノづくり」に貢献。
このストーリーのポイント
- 「地方の大きすぎない」工作機械メーカーとして、安田工業に惹かれる
- お客様の‟困りごと“の解決につながる技術・装置開発に取り組む
- 若手のうちから責任ある業務に挑戦し、成長する
工作機械(金属加工機)に惹かれて飛び込んだこの業界。チャレンジすることを後押ししてくれる安田工業の社風の中、伸び伸びと研究開発に取り組む。岡山は初めての土地ではあるが、仲間のサポートもあり、日々を満喫している。
安田工業株式会社
A.A
開発部 研究開発課
東京都出身
中央大学理工学部精密機械工学科卒業
2023年入社
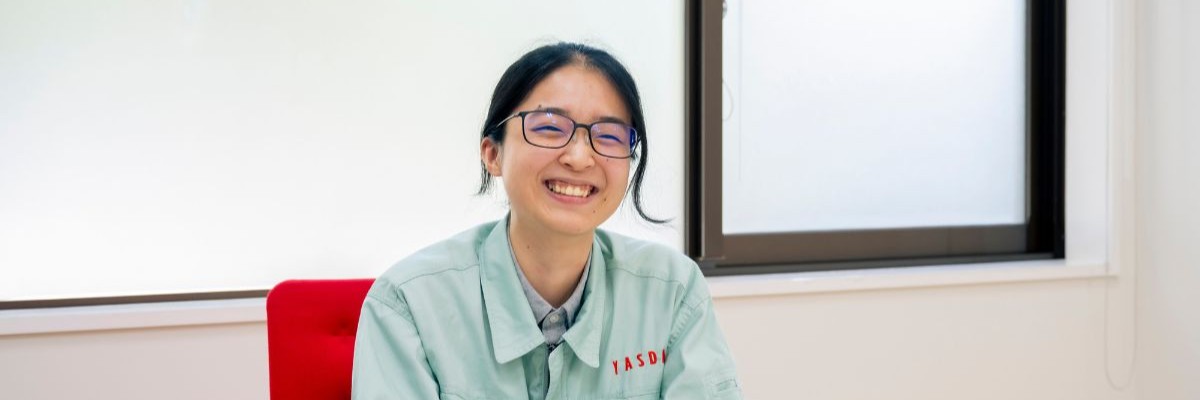
「地方にある、大きすぎない工作機械メーカー」という就活の軸に合致することで安田工業への入社を決める。研究開発部門に所属し、「今はないけれどお客様に必要とされているもの」の実現に取り組んでいる。
自動車づくりに挑戦した学生時代
生まれも育ちも、東京・多摩地方の日野市というところです。岡山とは何の縁もなかった私が、今、こうして安田工業で充実した日々を送っているのですから、就職とはまさに出会いだと思います。
ものづくりの世界に関心を持つようになったきっかけは、ガンダムでした。ロボットが好きで、子供の頃からガンダムのプラモデルを30体はつくったのではないでしょうか。自分としては文系の脳だと自覚しているのですが、ガンダムのおかげでものづくりに惹かれるようになり、大学では精密機械工学科でハードウェアについて学ぶことになりました。
学生生活で思い出に残っているのは、精密機械工学研究部という部活動です。私はここでサブリーダーとして、自動車製作に挑戦しました。
これは、部で伝統的に行われてきた取り組みで、毎年、自動車を手作りしては「Honda エコマイレッジチャレンジ」というコンテストにエントリーするというものです。エントリーは全国からあり、自作の車をサーキットで走らせて、1リットルのガソリンでどれだけ長く走れるかを競い合います。
自分たちで手作りしました。残念ながら入賞は果たせませんでしたが、夏休み返上で毎日集まって、仲間たちと汗を流したのはいい思い出です。
この体験を通じて、チームでのものづくりの進め方やコミュニケーションの取り方を学ぶことができました。会社ではプロジェクト単位でものづくりを進めますので、この経験は今に活きていると感じます。また、CADを独学で学んだことは、「本気でやれば何でもできる」という自信につながりました。これも、現在の仕事でプログラミングに取り組む際に活きている経験です。

ものづくりに対する真摯な姿勢に惹かれて
工作機械に惹かれたきっかけは、大学の講義でした。工作機械に精通されている先生が、とても楽しそうに工作機械について話されているのを見て、面白そうだなと思ったのです。
研究室を訪ねると、工作機械が金属の塊をゴリゴリと削っていました。私も少し触らせていただき、工作機械とはなんて凄いものなのかと驚きました。
この体験がきっかけで、就職活動は工作機械業界に絞って進めることにしました。
私が就職活動で定めた軸は「工作機械業界」「田舎」「中小企業」の3点でした。
東京で生まれて育った私は、学生時代も都心で過ごしました。それだけに自然や緑豊かな環境には憧れがあり、それが「田舎」という軸につながりました。通学で乗っていた満員電車には、もううんざりだったのです。
一方、ものづくりに携わりたいと考えていた私にとって、大きな組織では自分のやりたいことになかなか挑戦できないのではという危惧がありました。個人に大きな裁量を持たせるてくれる環境で働きたいと思い、それが「中小企業」という軸になりました。
この3つの軸で企業探しをした結果、見つけたのが安田工業。それまで知らない企業でしたが、会社のホームページがとても整ったものであることに惹かれました。ものづくりに対する真摯な姿勢はきっとこういうところにも反映されるに違いないと考え、この会社ならば丁寧なものづくりをしていると考えたのです。安田工業の売上高やシェアは業界の中でも決して大きくはありませんが、工作機械の加工精度の高さは高く評価されています。そうした優れた技術を育ててきた姿勢が、ホームページにも表れていると感じました。
面接では本社工場を訪ねました。私にとって人生初の岡山です。
工場では、それまで見たこともない巨大な機械が加工作業を行っており、それだけで私は圧倒されてしまいました。そして、絶対にここで働くんだと決めました。
岡山が人生で初めてであることに加え、一人暮らしも人生で初めてです。私はワクワクしながら岡山での暮らしをスタートさせました。
住んでいるのは会社から自転車で10分ほどのアパートで、岡山は晴れの日が多いですから、毎朝の通勤は快適です。
初めての土地であっても先輩方が美味しいご飯屋さんや病院などの情報を教えてくれるので、不便さは感じません。
生まれてからずっと暮らしていた実家を離れることに対して、両親は「やりたいことがあるなら心配せずに挑戦しなさい」と快く送り出してくれました。今も深く感謝しています。

「さすが安田工業」の言葉に胸を張る
入社して配属されたのが、開発部研究開発課です。平たく言うと、お客様と当社社員の「こういうことができたらいいな」に応えられる理想の機械をイメージし、その実現のために何が必要か、小さな課題を積み上げて研究し、解決に取り組む部署です。
例えば、社員が工作機械の評価のために主軸回転精度を計測する際、時間がかかるという課題を持っており、私はその解決のために測定を自動化するためのプログラムを開発しました。使った言語はPythonです。このプログラムによって、従来は計測のために半日は機械に張り付いていなくてはならなかったところ、アプリを約10分操作するだけで離れられるようになりました。おかげで社員の業務は大幅に効率化されました。
このようにお客様と当社社員の“困りごと”を解決するための理想の機械を追究することが私の部署のミッションです。
この業務効率化のテーマに取り組んだのは入社2年目。課長から「こんなテーマがあるけどやってみないか」と声をかけていただき、チャレンジしました。プログラミングについては高校時代に少し勉強したので基礎的なバックボーンはありましたが、それでも私にとっては大きなチャレンジです。勉強しながら開発を進め、思った通りに動かないときはバグを潰すという繰り返しで、ようやく完成させたときは思わずガッツポーズでした。
やはり入社2年目の出来事で思い出深いのが、展示会用の「自動芯出しサポート装置」の開発でした。これは多品種少量生産のものづくりを行うお客様に向けて、機械を止めて人が芯出しプログラムを作成することなく、自動で作成できる画期的な機能を搭載した装置です。この機能によって機械を止める必要がなくなるために生産効率が向上し、プログラムの人的ミスも排除できます。私が先輩と連携して開発したのは、この芯出しプログラムの作成・出力アプリでした。加工の完全な自動化という理想の機械の実現に向けて、一歩進めることができたと思います。試行錯誤の末にようやく開発したプログラムですので、まるで我が子を世に送り出したような達成感がありました。
その年の秋には東京ビッグサイトで行われた展示会に「自動芯出しサポート装置」を出品し、私も説明員として脇に立ちました。足を止めて説明を求めてくる来場者も多く、お話をすると「安田工業は凄いと改めて思いました」「さすが安田工業ですね」という言葉をたくさんいただきました。そのすべてが誇らしかったです。
この装置は、業務に関して有効な発明、考案をした従業員に対した贈られる「考案賞」という賞をいただくことができました。社員の中でも年に数人しか選ばれません。とても誇らしかったです。また、私の開発したプログラムについても、相当な効果のある提案に対して年間80件ほど贈られる「提案賞」をいただきました。
若手にも積極的に挑戦の機会を与え、挑戦した結果が失敗であっても責めることなく次の挑戦を促し、成功すれば全社的に称賛してくれる、安田工業のそんなカルチャーが大好きです。

安田工業ならではのファミリー感が心地いい
大きすぎない組織だから、若手にも責任ある仕事を任せてくれるのでは、という予想はその通りでした。工作機械業界と聞くと昔ながらの昭和なイメージを持つ方がいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはまったくなく、工場はきれいですし、女性も多数活躍しています。男女で仕事に差がつくことはまったくありません。
生活の面でも、地元出身の社員が様々なサポートをしてくれるので、不便さは感じません。とても温かい社風です。
安田工業はサークル活動も盛んで、私は登山部に入りました。初心者として一緒に山歩きに連れていってもらっています。ほかにもバレーやバドミントン、マラソンなどのサークルがあり、仲間づくりには最適です。
同期の仲間とは職種が違うのでなかなか仕事で一緒になることはありませんが、時々、みんなで一緒にご飯を食べています。同じ里庄町に、安田工業の社員が自由に使用できるレクリエーション施設があります。こんなことも都会の大企業ではありえないと思うので、安田工業ならではのファミリー感があります。
今後もお客様の“困りごと”解決に貢献する理想の機械づくりに取り組んでいきたいと思います。そのために専門性を磨き、まずはこれなら誰にも負けないという強みを持つ“T型人材”を目指します。そして、学びの幅を広げることで強みの数を増やし、“T”の縦棒を2本、3本と加えていきたいと考えています。
これからのキャリアが楽しみです。





