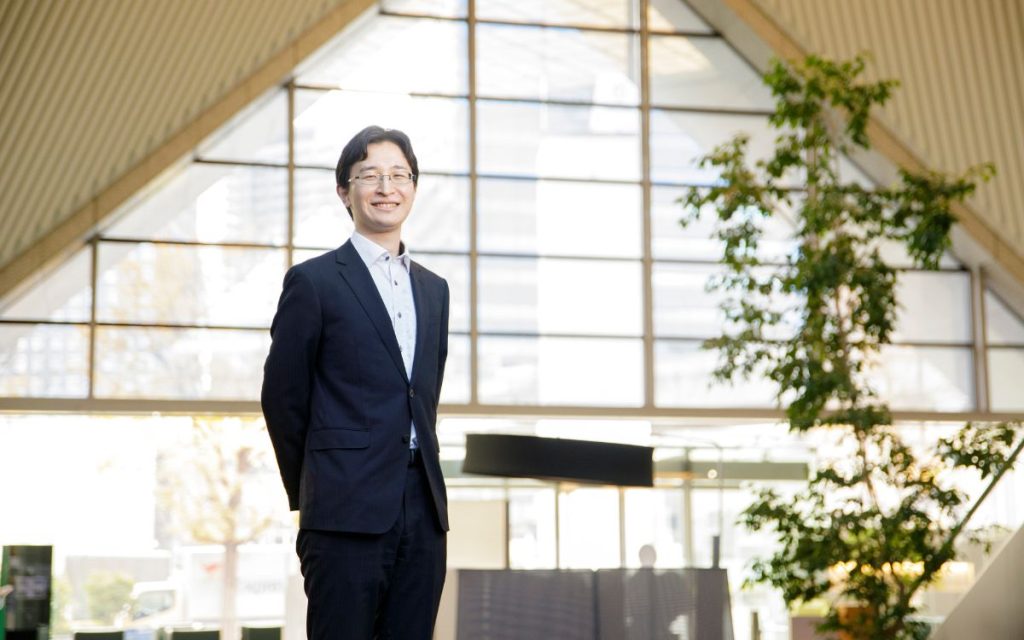
地域の暮らしを支えたいという志のもと、多様な業務経験を通じて自分を磨いていく。
地域の暮らしを支えたいという志のもと、
多様な業務経験を通じて自分を磨いていく。
このストーリーのポイント
- 人々の生活を裏側から支えたいとの思いで入構
- 多様な業務で「フラット35」の進化に携わる
- どんな業務に就いても、志がブレることはない
人々の暮らしの基礎となる住宅の取得支援や地域社会への貢献に魅力を感じて入社。現在はサービスのデジタル化に取り組む。どのような業務を担当しても、入構時の想いは変わらない。
住宅金融支援機構
髙山 和樹
地域業務統括部
個人業務デジタル化グループ
副調査役
2018年入構/商学部商学科卒
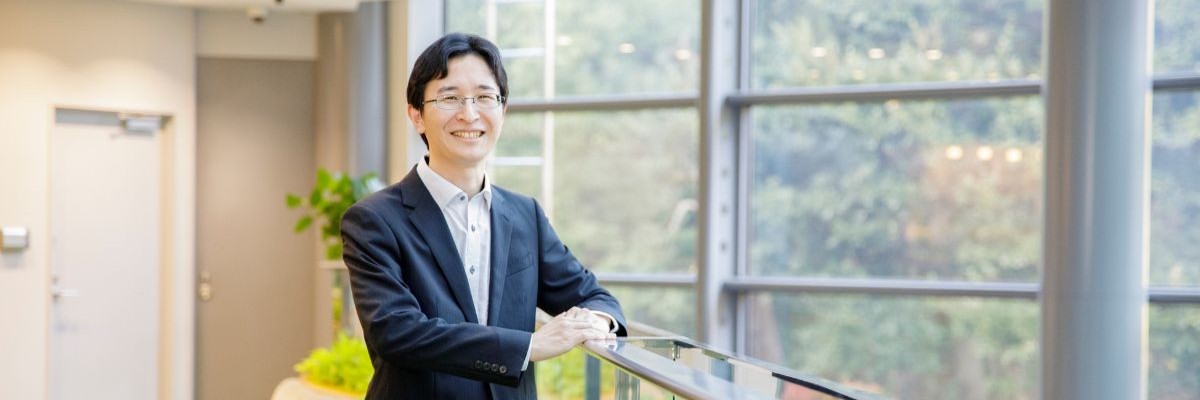
地域の暮らしを支える仕事がしたいと希望して入構。地域業務第二部まちづくりグループ、業務管理部、地域業務統括部フラット35運用グループを経て、2023年10月より半年間の育児休業を取得。2024年4月に復職し、現職に。デジタル化関連業務に携わる。
自分の“軸”にマッチしていると感じて
学生時代、サークル活動としてコミュニティカフェの運営に携わりました。場所は古い団地の中。商店街にもシャッターが目立つような環境でしたが、一角に気軽にコーヒーの飲めるカフェを置くことで、地域に活気を取り戻せないかと考えたのです。
実際、カフェにはご高齢の常連さんが集まって、井戸端会議に花を咲かせてくれました。その笑顔をきっかけに地域も次第に元気を取り戻し、ハロウィンのイベントが開催されたり、商店街に人通りが戻ってきました。
活性化できたと言い切れるかはわかりませんが、地元の人々の交流を通じて、地域の暮らしに寄り添うことはできたと思っています。
このコミュニティカフェでの経験により、地域の暮らしを裏側から支える仕事がしたいという志で就職活動をスタートさせました。具体的にはまちづくりの推進役としてのデベロッパーや都市開発に力を入れている鉄道会社、あるいは公的金融として人々の生活を支援する政府系金融機関です。そうした中で知ったのが、住宅金融支援機構でした。
それまで私は住宅金融支援機構のことは知りませんでした。企業研究を進めると、人々の暮らしの基礎となる住宅取得を支援する『フラット35』、民間の金融機関が融資をしづらい市街地の密集地域や再開発への融資を行っている『まちづくり融資』などに魅力を感じ、地域の暮らしを下支えする仕事がしたいという私の“軸”にマッチしていると感じるようになりました。
何よりもその名称のとおり、住宅金融支援機構はミッションと業務内容が明確です。配属先によって希望とはほど遠い業務を担当せざるを得ないという心配はありません。この点は大きな魅力でした。

前例にこだわらずチャレンジできる
最初に配属されたのは、地域業務第二部まちづくりグループでした。担当したのは、子育て世帯向けの賃貸住宅を計画しているオーナーや事業者からの融資申し込みに対する受付業務です。賃貸住宅としての収益性を考えればワンルーム等の単身者向けが有利なのは間違いありません。しかし、ファミリー層向けの優良な賃貸住宅を増やしていくことは地域活性化という点でも大切なことですから、融資の相談を通じてオーナー等に対してその計画変更を働きかけていくんです。
相談の中にはサービス付き高齢者住宅(サ高住)もありました。当時はあまり認識されていなかった施設形態で、私もここで初めて知りました。私が融資の相談に携わったサ高住が竣工したときは実際に現場を見学に行き、地域の福祉におけるセーフティーネット的な貢献ができたことを実感。“金融”という機能を通じて地域の暮らしを下支えしたいという私の想いがカタチになったことは、大きな喜びでした。
入構5年目に地域業務統括部フラット35運用グループに異動しました。機構のメイン商品である『フラット35』は我々がお客様に直接販売するのではなく、銀行やモーゲージバンク(住宅ローンを専門に取り扱う会社)等の民間の金融機関に販売をお願いしています。その際にスムーズに業務を行っていただけるよう、マニュアル作成などのサポート業務に携わりました。
『フラット35』では、国の政策課題を解決するために新しい制度が取り入れられることがあります。金融商品は概して複雑であり、しかも民間の金融機関は幅広い商品を取り扱っているため、制度改正に伴う『フラット35』の仕様変更等をすぐに理解することは簡単ではありません。『フラット35』を国民の皆さんに広くあまねくご利用いただくためにも金融機関の協力は不可欠であり、正しい取り扱いのサポートを行いました。
このときに直面したのが、コロナ禍です。
それまでは機構の支店に我々が赴いて、地域の金融機関の皆さまに向けた説明会を行っていたのですが、コロナ禍によってそうしたサポートができなくなってしまいました。やむなくWeb会議に切り替えたところ、通信状況によってフリーズしたり、音声が聞き取れなかったりといったトラブルが頻発。そこで工夫したのが、資料を動画にして、人工音声での説明を加えるというやり方です。それをアーカイブにすることで金融機関の方は、電波状況等を気にすることなく、必要なときにいつでも資料を確認できるようにしました。
住宅金融支援機構と聞くと、堅苦しい組織のように思われがちですが、実際は前例にとらわれずに柔軟に対応しようとするカルチャーがあります。上司も「どんどん新しいことにチャレンジしようよ」と口にしていましたし、私も伸び伸びと取り組むことができました。アグレッシブな組織風土は、住宅金融支援機構の魅力の一つです。

デジタル化に向けた取り組み
現在私は、業務のデジタル化を進めるために新たに発足した部署で、「フラット35Web申込サービス」を担当しています。既に「フラット35電子契約サービス」が導入されており、これによってお客様のお申し込みから契約までの一連の流れが電子化されました。今はデジタル化されたこれらのサービスを金融機関にスムーズに使っていただくためのサポートを行っています。
デジタル化において技術的な面を担うのは外部のITベンダーで、私は発注者としてベンダーと協力しながらプロジェクトを進めていく立場です。ベンダーは技術には詳しくても『フラット35』の仕組みや規制等には精通していないので、私がそこを紐解いてお伝えし、スムーズなシステムの開発をサポートしています。
「フラット35Web申込サービス」は2025年1月にリリースされました。私はリリース前から金融機関へのサポートに走り回りましたが、自分の携わった仕事が世の中に出ていくことにワクワクしながら取り組んだものです。リリース後も、金融機関からの問い合わせや想定外のトラブルなどに備え、緊張感を持って取り組みました。
私は商学部の出身ですから、特にITについての専門的な知見があったわけではありません。ですからデジタル関連の業務は、私にとって大きなチャレンジでした。業務を通じて最新のDXについて学ぶことも多く、大きな刺激を受けながら取り組んでいるところです。
このように住宅金融支援機構では、数年おきに異動を繰り返すことで常に新しい仕事に挑戦することができます。自分をアップデートできる感覚は、大きなやりがいです。
現在は金融機関やお客様の手続きのデジタル化に携わっているので、次は我々自身の業務のDXに挑戦したいと思っています。本格的なデジタル化はこれから。課題は多くあると感じており、チャレンジしがいのあるテーマです。

半年間の育児休業取得で、仕事への意識も変わる
入構6年目の夏、初めての子どもが生まれました。男の子です。それに際し、私は半年間の育児休業を取得しました。
取得に際して上司に相談したところ、「ぜひ取ってくれ」と強く背中を押されました。私が抜けることで周囲の業務の負荷が重くなるのではと心配したのですが、私の穴埋めに職員を補充するという人事的なサポートもいただき、周囲に迷惑をかけるのではという心苦しさもなく、安心して育休に入ることができました。
始まる前は半年って長いと思っていたのですが、実際はあっという間でした。子どもの成長スピードに驚くとともに、妻の大変さを目の当たりにしたことで、育休を取得して本当によかったと思いました。
子育てというのは貴重な経験で、人生を豊かにしてくれることは間違いありません。ぜひこれから入構される男性の皆さんにも、取得をお勧めします。今は妻も働いていますので、できるだけ早く帰って育児の手伝いをしようと、仕事の効率化を強く意識するようになりました。残業をせずに済むよう、仕事の取り組み方が変わってきたと思います。私にとって大きな変化です。
住宅金融支援機構に入構してよかったと改めて感じるのは、住宅金融という分野に特化した仕事ができるという点です。業務そのものは多岐にわたりますが、どの仕事も「住宅金融を通じて地域の暮らしを下支えする」という点に変わりありません。ですから常に自分が何のために働いているのか、深い納得感のもとで仕事ができるのです。しかもそれが国の施策の一翼を担っているという実感につながっています。
今後、どの部署に異動してもこの手応えは変わらないでしょう。
金融機関やデベロッパーの方と接したり、時には商品の利用者と接したり、様々な人とコミュニケーションをとる機会が多い仕事です。住宅金融の制度や仕組みをつくることは大切ですが、コミュニケーションを通じてその普及を推進していくことも重要です。ですから入構をお考えの方には、ぜひコミュニケーション力を磨いていただけたらと思います。
そして何よりも大切なのが、よりよい住環境の実現を通じて社会に貢献したいという強い想い。国の政策の実現を担っている使命感こそ、私たちに最も求められるものでしょう。




