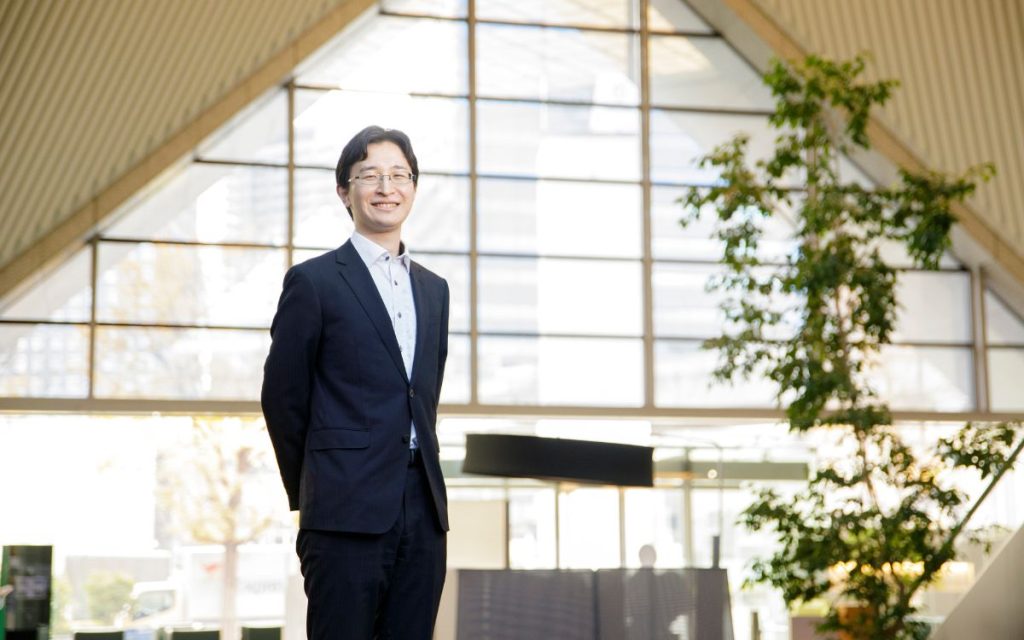ジョブローテーションは挑戦のチャンス。未知の業務だからこそ大きな成長が得られる。
ジョブローテーションは挑戦のチャンス。
未知の業務だからこそ大きな成長が得られる。
このストーリーのポイント
- 生き生きと働く先輩の姿に惹かれて入構
- 商品の創設やデジタル系教育などにチャレンジ
- 多くの女性に、後に続いてほしい
住宅金融支援機構
田中 紀子
総務人事部
人事グループ
推進役(人材開発担当)
2002年入構/法学部卒

我が国の住生活の向上に貢献できる点、先輩職員が生き生きと働いている点に惹かれて入構。北関東支店、首都圏支店、業務推進部、経営企画部、コンプライアンス・法務部、業務企画部、まちづくり業務部、広域法人業務部を経て現職。職員の人材育成に携わる。
社会の役に立つ仕事がしたい
「住宅金融支援機構」と聞くと、業務が限定されていて、狭い経験しかできないような印象を受ける方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際はそんなことはなく、ジョブローテーションを通じてさまざまな経験をすることができます。
私自身も数年に一度の異動を経験し、異動のたびに新たな経験や知識を習得できました。それがまさに自分の成長の実感に結びついています。この点は住宅金融支援機構の大きな魅力でしょう。
就職氷河期世代の私は、業種や職種にこだわらず、多様な企業を見て歩くことで就職活動をスタートさせました。メーカー、鉄道会社、エネルギー業界、金融関係と、生涯二度とこれほど幅広い企業を見ることはないだろうと思ったものです。
その過程で次第に自分の“軸”もはっきりしてきました。それは、何らかの形で社会に役に立つ仕事がしたいということ。広くあまねく、世の中を支えたいと思ったのです。
そんな中で出会ったのが当時の住宅金融公庫、つまり現在の住宅金融支援機構です。当時は名前も業務内容も知らなくて、政府系金融という一点に惹かれて足を運びました。政府系だからお役所みたいな堅いところだろうなあといった程度の認識でもありました。
ところがお目にかかった先輩職員が大変に魅力的で、生き生きと楽しそうに仕事についてお話をしてくれたんです。その姿を見て、こんな方たちのいる組織なら自分も楽しく働けると感じ、入構を決めました。いわば直感です。この判断に間違いはなかったと、今振り返っても強く思います。

国の政策の一翼を担う醍醐味
入構以来、様々な経験を重ねてきた中で強く印象に残っているのは、13年目から16年目に所属していた業務企画部での仕事です。大変な仕事ではあったのですが、その分、大きく成長できたという実感がありました。
私が担当したのは『フラット35子育て支援型、地域活性化型』の創設でした。それまで『フラット35』は住宅の性能、つまりハードに着目して融資の金利を引き下げていましたが、新しい商品は子育てや地域活性化というソフト面を金利引き下げの要件にするというものでした。国の政策を実現しつつ良質な住宅の普及を後押しするという点で画期的な商品ではあったのですが、実現は簡単なことではありませんでした。
住宅金融支援機構は政府系金融機関ですから、国の予算から出資金や補助金をいただいており、商品の創設や改善に際しても国の理解が必要です。『フラット35子育て支援型、地域活性化型』においても国土交通省、財務省との調整を行わなくてはならず、私もその調整業務に携わることになったのです。
画期的な商品であるだけに国土交通省への説明には十分な準備が必要で、資料の作成等でかなり忙しかったのを覚えています。また、上司と一緒に霞ヶ関に足を運び、なぜこの商品が国民の住環境向上に資するのか、国の住政策とどのようにリンクするのか、ご理解いただくために説明を繰り返しました。国土交通省にご理解いただいた後は、一緒に財務省を訪ねて予算措置の理解を得るための説明にも同席しました。
まさに国の中枢で、国を動かしている方々との折衝は非常に貴重な経験となりました。
実は私が異動するまで、業務企画部で女性が活躍したことはなかったようです。私の異動に際しては他にもう1人の女性がいましたが、ここで頑張ることで後輩の女性に新しい道を開いてあげられるという想いがありました。
また、国の住政策を実現するための一翼を担っている手応えは大きく、本当にダイナミックな仕事だと実感しました。視野もずいぶん広がったと思います。新しい商品の創設に携われるチャンスは、誰にでもあるわけではありません。そのような貴重なチャレンジをさせてもらったことに感謝するとともに、ジョブローテーションを通じて多様な経験ができる住宅金融支援機構の魅力を改めて感じました。

人材育成を通じて組織の発展に貢献する
現在私は総務人事部で職員の育成に携わっています。以前から人材育成に取り組んでみたいと考えて希望をしていたのですが、それが叶っての異動でした。
住宅金融支援機構は人材育成に力を入れており、入構後3年間を機構人材育成期間と位置付けてOJTや集合研修を実施。資格取得、通信教育、ビジネススクール通学等の自己啓発の支援制度も整っています。さらに金融・証券関連専門講座、海外研修等の公募型研修もあります。
住宅金融支援機構では新卒採用を一時的に抑制していた時期があり、その分、若手にどんどん成長していってほしいと考えています。そのため育成制度には特に力を入れており、私も若い人材の成長を後押しすることに大きなやりがいを感じています。
実際、私が総務人事部に異動してきた初日に担当した業務が新入社員の導入研修でした。講義を行ってくれたのは外部の講師や各部署で活躍する職員で、私は不安でいっぱいの新人たちに声をかけたり、同期同士がコミュニケーションできるようにサポートしたりといったことを行いました。異動してすぐでしたので、私にとっても大きなチャレンジだったのです。しかし2週間の研修期間を終える頃には全員の表情が目に見えて変わり、社会人としてスタートするにふさわしい佇まいになっていました。その姿にホッとすると同時に、若手の成長するスピードに驚き、そして喜びを実感しました。
今、特に力を入れているのがIT・デジタル人材育成のための取り組みです。住宅金融支援機構自身が本腰を入れて業務のDX化を推進していることもあり、職員にも関連するスキルを身につけてもらおうと、IT・デジタル化に関連する講座などを行っています。
IT・デジタル関連は職員にとってあまりなじみのない分野のため、「自分には関係ないから」「難しそう」という反応を示す方もおり、職員にいかに関心を持ってもらうかが課題でした。そこでどんな方が受講したとか、こういう業務に役立ったとか、様々なケースを社内イントラネットや階層別研修の機会をとらえて紹介。できるだけハードルを下げようと工夫しました。だからこそ「受講してよかった」「仕事に役立っている」という声を聞くと、とても嬉しく感じます。
私自身もこの2年でITパスポート、情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者といった資格を取得しました。人材育成に興味はあったものの、IT・デジタル関連のスキルは自分には関係ないと思っていたので、自分にとってもこれは大きなチャレンジとなりました。自分が理解できないものを人に勧めることに抵抗があったから、まず自分が学んでみようと考えたわけです。
以前の私からすれば想定外の学びではありましたが、これも異動したから得られた成長です。まさにジョブローテーションは成長のチャンスであることを実感しています。

管理職だからこそ見える景色がある
入社17年目に管理職に昇進しました。
これも入構時にはあまり意識していませんでした。しかし『フラット35子育て支援型、地域活性化型』の創設等に携わった際にリーダー的な業務を経験してマネジメントの仕事のやりがいに気づき、そこから管理職に昇進することを意識するようになりました。
管理職になったことで感じるのは、自身の視野の広がりや高さです。特に部下がどのような環境で日々の業務をこなしているかがよく見えるようになり、例えば子育てや介護との両立に苦労しているといった事情もわかるようになりました。管理職の使命の一つは部下が働きやすいように環境を整えることですから、会社の支援制度や福利厚生制度の活用を促しています。
また、女性の活躍推進に力を入れており、女性の管理職育成にも取り組んでいます。残念ながら住宅金融支援機構における女性の管理職の比率はまだ低く、その改善は大きな課題となっています。後輩の女性たちが「私なんか」と思わず、管理職を目指してくれるよう、私自身がロールモデルにならなければと思っています。かくいう私自身「私なんか」と思っていましたから、「そんなことないよ、あなたにもできるよ」ということを、私の背中で伝えられたら嬉しいです。
今後も何度か異動を経験するでしょうから、新しい挑戦、新しい経験を積んで、自分の幅を広げていきたいと思います。
例えばIT・デジタル化に関する知識を更にブラッシュアップしたり、以前経験した部署で管理職をやってみたいという考えもあります。これからの挑戦が楽しみです。
いつの時代も女性にとって結婚、出産といったライフイベントとの両立は大きな課題です。住宅金融支援機構では両立支援のための制度が整っており、男性も積極的に育児休業を取得するようになりました。また、親族家族で子育てを支えることができるよう、令和6年4月に新たに親族育児参画休職制度を創設しました。育児をしながら働いている職場の仲間への理解が深まることを期待してできたもので、若い職員にとっては自分の育児のシミュレーションにもなるでしょう。他社にはあまりない、画期的な制度ではないでしょうか。
このように住宅金融支援機構では職員の働きやすさにつながる制度が充実していますので、ぜひ多くの方にドアを叩いていただければと思います。