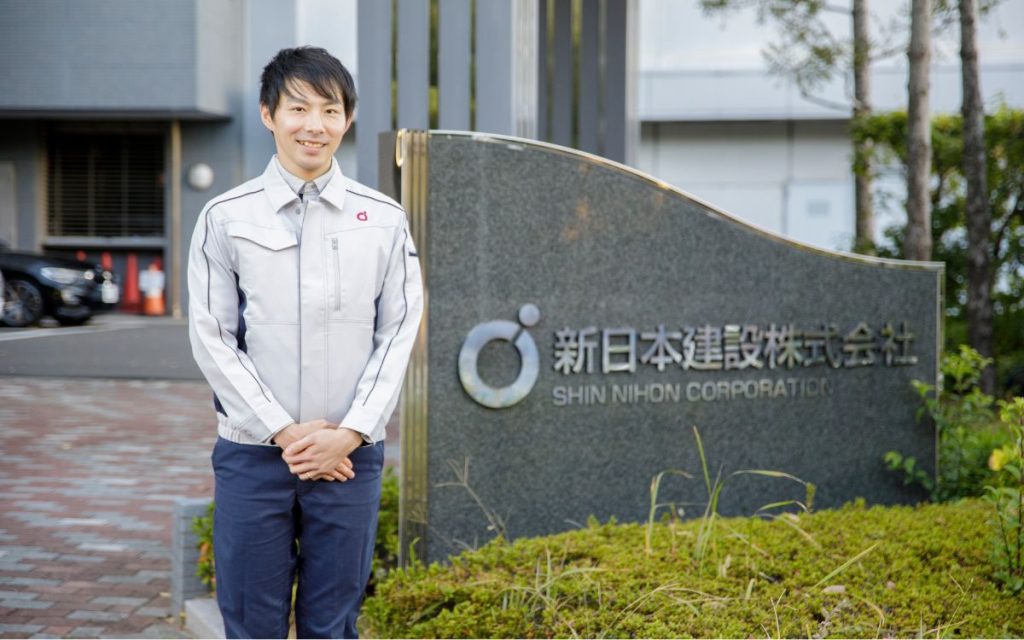経験したすべてが施工管理としての力になる。新日本建設で得られる、成長の実感。
経験したすべてが施工管理としての力になる。
新日本建設で得られる、成長の実感。
このストーリーのポイント
- 千葉を拠点に働きたいと希望して入社
- 職人との信頼関係を大切にものづくりに取り組む
- 自分の携わった建物が街に溶け込んでいく喜び
建物の施工現場を管理するのが施工管理のミッション。ものづくりの最前線だ。人を動かし、力を合わせて建物をつくりあげていく醍醐味がある。
新日本建設株式会社
三原 諒
工事統括本部
第二工事本部 工事第一部
2020年入社
生産工学部環境安全工学科卒

山形県出身。学生時代を千葉県で過ごし、そのまま千葉で働きたいと考えて新日本建設に入社。施工管理として多くの物件の施工に携わる。将来の目標は現場所長になること。
地域密着の働き方
山形県に住んでいた小学校1年生で始めた野球を、大学卒業まで続けました。大学2年生のときは、新日本建設の本社近くにある「ZOZOマリンスタジアム」で千葉県の大学のリーグ戦を戦いました。このときは代打で出場し、そのまま外野手のポジションに入りました。いい思い出が刻めたと思っています。
当時のチームメイトとは、先日も仲間の結婚式で再会しました。今も時々、一緒にプロ野球観戦を楽しんでいます。
中学生の時、東日本大震災を経験したことから、人々が安心して暮らせる場所を作りたいと強く思うようになり、建設の世界にかかわってみたいと思うようになりました。住まいは社会の重要なインフラです。それを支えることにやりがいを感じました。
就職活動では新日本建設のインターンシップに参加し、施工現場を体験させてもらいました。千葉駅西口再開発の現場で、その大きなスケールにはワクワクしたものです。ぜひ自分も施工現場で働いてみたいとの思いを強くしました。
ただ、いわゆるスーパーゼネコンだと全国転勤が当たり前。全国津々浦々、1つの現場が終わったら次の現場へと移っていかなくてはなりません。私はそうした働き方ではなく、1つの場所にじっくりと腰を落ち着けてキャリアアップする生き方がしたいと思いました。その点、地域密着の新日本建設なら現場は一都三県に限定され、転勤もありません。首都圏在住で長く働けることに惹かれ、入社を決めました。同じような動機で入社する社員は、非常に多いと感じています。

いかにメリハリをつけて管理するか
現在私は都内・浅草の7階建てマンションの現場で、施工管理を担当しています。ポジションとしては現場所長の次の次席となります。施工管理の役目とは、工期や予算、品質、安全などを管理し、工事がスムーズに進むようにコントロールすることです。実際に作業をするのは職人さんたちですから、その方々を管理し、事故が起こらないように工事を進めていくことが求められます。
職人さんたちはその分野のプロフェッショナルぞろいで、腕は確かです。しかし人間は誰だって慣れから油断することもあるでしょう。ベテランの職人さんも同じです。万一のうっかり事故が発生しないよう、現場全体に目を配り、職人さんたちの動きを的確に把握しておくことが、施工管理として大切な仕事です。
慣れは、やはり一番怖いです。現場の安全を守るため、ベテランの職人さんにも時にはシビアなことも言わなくてはなりません。ただ、厳しすぎても反感を買いますし、だからといって甘くしてはスキが生じて安全面もおろそかになりがちです。このあたりのバランスは難しいですね。施工管理の腕の見せどころかもしれません。
私が心がけているのは、締めるときは締め、緩めるときは緩めるというメリハリ。今はそのちょうどいい部分を探しているところで、自分なりのスタイルを模索中です。
施工現場というのは面白いもので、施工管理の担当者が変わると現場の空気も一変するものです。自分の持ち味を反映しやすいのが、施工管理という仕事の面白さでしょう。私ならではの持ち味をどのように見つけ、発揮していくか、これからの課題です。
施工管理としての一番の喜びは、やはり竣工の瞬間です。何もなかった場所に新しい建物ができて、周囲の景観も変わっていく、そんな手応えが嬉しいです。
もっとも最近では、喜びというよりも安堵感の方が大きいかもしれません。それこそ1年目の時は完成した建物を見上げて「これをオレがつくったんだぜ」という誇らしさを感じたものでしたが、今は安全管理により意識を傾けるようになったため、終わった時にはまずホッと感じるようになったのでしょう。それでも建物が完成して、ここでご購入者の新しい暮らしが始まるという思いは、言葉には表しきれないものです。
新日本建設は「自社製販一貫体制」が特徴ですので、販売後の内覧会に私も同席することがあります。今も覚えているのは1年目に経験した内覧会で、お父さんはベランダで「景色がいいね」と笑い、お母さんは「キッチンが素敵」と嬉しそうで、そして小学生くらいの女の子が楽しそうに走っていました。まさに幸せなファミリーそのままの雰囲気で、このマンションづくりに携われて本当によかったなと思ったものでした。

辛い経験も必ず自分を成長させてくれる
施工管理として私が最も大切にしているのは、職人さんとの信頼関係づくりです。ほとんどの職人さんは私より年上のベテランで、知識や経験も私より豊富なのですが、信頼関係ができていれば年下の私のこともリスペクトしてくれます。それには当然のことながら私がそれ以上に職人さんをリスペクトすることが重要になってきます。
個性豊かで主義主張のはっきりした方も多く、少しでもリスペクトの気持ちが欠けるとすぐに伝わってしまう怖さはありますね。私は長年野球で先輩後輩の関係を大切にしてきましたし、礼儀や言葉づかいにも注意するように心がけています。決して私たちが上で、職人さんが下の関係ということはありません。
今まで印象に残っているのは、2年目から3年目にかけて担当した現場です。新日本建設の「エクセレントシティ」シリーズのマンションで、3棟200世帯という大規模な物件の現場でした。職人さんも常時150人以上はいたと思います。
この現場では毎日が苦労の連続でした。例えば人のやりくりがうまくいったとしても天候がよくないので作業がストップしたり、作業がストップすると職人さんたちの機嫌が悪くなったり。あるいは危険な箇所があったので安全のために動線を変えたところ、スムーズな動きができなくなって作業効率が落ちたり。こんな具合に大小様々なトラブルが頻出し、上手くいかないことが多く、落ち込む日々でした。
非常に辛い思いをした現場でしたが、おかげで学んだことも多かったです。
私の持ち味はポジティブさで、どんな状況でも物事を楽観的にとらえるタイプです。ポジティブというのはいいことなんですが、建設現場で楽観的すぎることはマイナスです。むしろネガティブなくらい、常に最悪のことを想定するぐらいでちょうどいいのです。
この思いは、次の現場でより確かなものになりました。この現場を預かる所長は、どんなときでも2手先、3手先を読んで、前もって手を打てる方でした。その姿を近くで見ていた私は、ネガティブなことを想定できるから先手を打てるのだという思いを一層強くしたのです。
当社に限ったことではなく、どんな建設現場でも今は外国人の方が大勢働いていて、言葉の問題からコミュニケーション不足が深刻化しています。だからこそ常に先回りして準備しておくことがますます重要になっていくでしょう。人と接するときにはポジティブでありつつ、一方でネガティブな視線で先手を打っていく、そんな私なりの施工管理像を確立したいと考えています。

現場のDXにも挑戦したい
若手に背伸びをさせる社風のある新日本建設では、30代前半で所長になるケースが珍しくありません。先日はついに20代の所長も誕生。人が成長できる環境であることは間違いありません。
私自身も次は所長を目指しています。そのためには一級建築施工管理技士に合格する必要があり、今は試験を受けて結果を待っているところです。取得後は報奨金や資格手当も支給されます。成長できる環境だけでなく、学びを促す制度も整っているのです。
人手不足と作業員の高齢化が深刻な問題となっている建設現場では、作業の効率化や省力化が必須で、DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みが急務となっています。新日本建設でもテクノロジーは積極的に活用し、無人で現場を見回るシステムやVR(バーチャル・リアリティ)の導入などを進めています。この点は今後の施工管理においても、意欲的に取り組んでいきたいと考えています。
施工管理の役目はますます重要なものとなっていくことでしょう。
私が一緒に働きたいと思っているのは、ものづくりに対する熱意と、コミュニケーション力を備えた方です。
私たちが建物が完成するまでの管理を担当しますが、向き合うのはモノではなく人です。コミュニケーションを通じて職人さんと良好な関係を築くことが、ひいては優れた建設物の実現につながっていくのです。
自分の持ち味を大切にしながら、大きなものづくりに携わりたいと考えている方に、ぜひ挑戦していただきたいと思います。