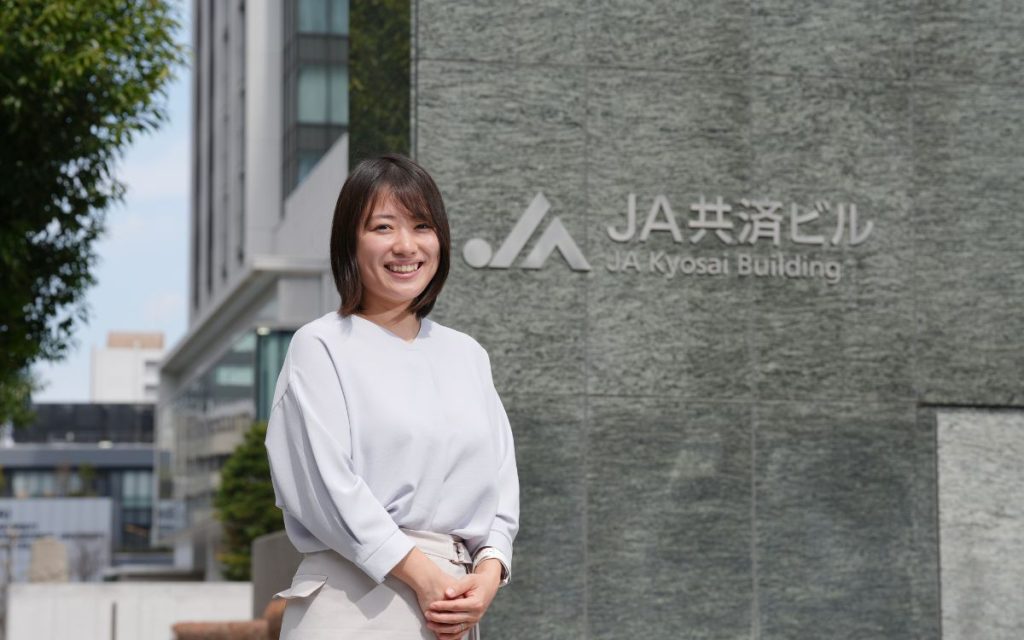
一人で悩むのではなく、大切な人たちと共有しあう。そう考えて、仕事と育児の両立に取り組む
一人で悩むのではなく、大切な人たちと共有しあう。
そう考えて、仕事と育児の両立に取り組む
このストーリーのポイント
- より多くの人の暮らしを支えることができると判断し、JA共済連に入会
- 業務経験を積んだ後、結婚・出産・育児など人生の転機を迎える
- 2年間の育休を 経て職場に復帰。周囲に支えられながら仕事と育児の両立を目指す
JA共済連では地域社会への貢献を実感でき、温かい社風の中で成長を感じられる。自身の成長が、地域社会の安心に繋がっている。そう実感できる日々に、誇りを持っている。
充実した福利厚生制度のもとで仕事と家庭の両立を目指せる、JA共済連はそんな魅力的な組織でもある。「今日も、誰かの『もしも』を支えるために全力を尽くそう」。そんな決意を新たな業務に臨む、女性職員の活躍ストーリー。
JA共済連(全国共済農業協同組合連合会 全国本部)
佐藤 弥莉
事務企画部 短期事務グループ
2015年入会
農学部 食料環境政策学科卒

幼い頃から、祖父母や親戚の家を訪ねるたびに、その土地の温かさや自然、そしてそこで営まれる農業に憧れがあった。しかし、実際に農業を担うことへの自信はなかったため、これまで培ってきた自分の強みを活かし、別の形で農業や地域社会に貢献したいと考えるようになる。そうした中、「相互扶助」の理念を掲げ、地域に根差した事業を展開するJAグループに魅力を感じ、JA共済連のみならず、JAグループの各団体に応募。自身の好きなこと、本当にやりたいことを実現したいという強い想いと、幼い頃からの憧れと就職活動を通じて抱いた想いを胸に、第一志望であったJA共済連でその夢を叶えようとしている。
農業とつながりの深い仕事をしたい。その一心でJA共済連へ
私が農業に関わる仕事に興味を持った原点は、幼い頃に遡ります。父方と母方の実家が地方にあり、農業や畜産業を営む親戚の元によく遊びに行っていました。そこで過ごした経験を通じて、土に触れ、作物が育つ喜び、そして人々の生活を支える農業の重要な役割を肌で感じてきました。大学では農学部に進み、将来は「農業とつながりの深い仕事に就きたい」という強い想いを抱くようになり、JAグループ各団体への就職を検討しました。
数あるJAグループの中で、私が第一志望としたのはJA共済連でした。それは、単に農家の方々だけでなく、地域社会全体、そしてより多くの人々の暮らしを「ひと・いえ・くるま」の総合保障を通じて支えることができると強く感じたからです。実際に選考に臨む中で、面接は非常に和やかな雰囲気で、飾らない自分を受け入れてもらえたように感じました。さらに、大学のOB・OGであるJA共済連の職員の方々との対話の機会を何度も設けていただき、仕事内容や職場の雰囲気、働き方について深く理解することができました。お会いする職員の方々が皆親切で、親身になって私の話を聞いていただいた点が他社にはない温かさであり、私の入会を決意させる大きな要因の一つとなりました。
内定をいただいた後も、さまざまな職員の方からお話を伺い、JA共済連の事業が多岐に及んでいることを理解しました。その中で、「できることなら、地域の方々と接点を持って色々なお話を聞いたり、JA共済連の理念や活動内容を知ってもらえる職務につけたら良いな」という想いが高まっていきました。
実際に配属となったのは、システム開発部短期グループ(当時の部署名)です。システム開発といっても、自分がSEとしてシステムを開発していくのではなく、ベンダーらの協力を得ながら、JA共済連の事業に絡むシステムの構築を取りまとめていく仕事です。正直なところ、配属された時は不安でいっぱいでした。「システムに関する知識は全くのゼロ。むしろ、私には最も向いていない仕事なのではないか」とさえ感じてしまったほどです。それでも、「まずは与えられた環境で精一杯頑張ってみるしかない」と気持ちを奮い立たせ、新たな挑戦に身を投じることにしました。
それからの毎日は、まさに勉強の連続でした。会議に参加しても、飛び交うシステムの専門用語がまるで異国の言葉のように聞こえ、わからないことばかりでした。しかし、幸いなことに、グループの先輩方は皆、私が理解できるまで本当に丁寧に、根気強く教えてくださいました。入会して2年ほど経った頃、ようやく専門用語が少しずつ理解できるようになり、3年目には担当者としてシステム開発の案件を任せていただくことができ、そこで初めて仕事の面白さを感じることができました。具体的に担当したのは、火災共済の仕組改訂に伴うシステム対応でした。そして5年目を迎える頃には、グループ内では在籍期間の長いメンバーとなっていたため、現場の実務に関しては、上司や先輩から大きな裁量を委ねられるようになっていました。スタート時は「苦手だ」と感じていたシステム開発の仕事でしたが、この5年間で、なんとか一人前のレベルまで到達することができたと、今では自信を持って言える気がしています。

キャリアの転換と育児との両立。周囲の支えに感謝して
入会して6年が経ち、私はキャリアの転機を迎えました。6年目に結婚、そして7年目には出産という人生における大きな出来事を経験し、その後2年間という育児休業を経て、現在は職場に復帰し、仕事と育児の両立に奮闘しています。
結婚した時期と同時期に私はシステム開発部短期グループから事務企画部短期事務グループへと異動しました。新しい部署は非常に忙しく、「早く仕事を覚えたい」と焦る気持ちと、「これからの出産や育児を考えた時に仕事と育児をどう両立していけば良いのだろうか」という不安でいっぱいでした。
そんな時、私の背中を押してくれた二人の上司の存在は大きかったです。異動後、課長からは、「仕事に没頭するだけでなく、家庭のこと、キャリアのこと、自分がどうしたいかも考えてみたらどうか。ご主人ともよく相談して」という温かいアドバイスをいただきました。当時は仕事中心の生活を送っていたため、この言葉は私の心を軽くし、新たな一歩を踏み出す勇気を与えてくれました。また、育休中に上司となった女性課長は、管理職として働きながら四人のお子さんを育ててきたという経験豊富な方でした。その方のお話を聞く中で、「私にもできるかもしれない」と希望を持つことができ、「とにかくやってみよう」という前向きな気持ちになりました。
育休も、上司や人事担当の方々から定期的に状況確認のご連絡をいただき、とても心強かったです。特に、私の育休期間は2年と比較的長かったため、「仕事の進め方や職場の環境が大きく変わってしまっているのではないか」という不安がありましたが、気にかけてもらえていることを実感でき、安心して育児に専念することができました。
職場復帰後、仕事と育児の両立は想像以上に大変でした。現在、私は夫の勤務地に近い千葉県袖ケ浦市に住んでおり、JA共済連の全国本部(都内・永田町)までの通勤には往復で四時間もかかります。それでも、「皆に一日も早く追いつきたい」という思いから、フルタイム勤務を続けています。そのため、毎日が時間との闘いです。
このような状況の中、本当にありがたかったのは、職場の上司や同僚からの温かいサポートと、夫の協力です。もしこれらの支えがなければ、今の両立は非常に困難だったと思います。職場の皆さんには、育休復帰したばかりの私を常に気遣っていただき、「育休明けなのに、こんなにも仕事をしてくれてありがとう」という感謝の言葉をかけていただきました。私自身は、むしろ周りの皆さんに助けられていることへの感謝の気持ちでいっぱいなのですが、育休明けであることを常に理解し、配慮してくれる職場の環境に心から感謝しています。
だからこそ、私自身も仕事をする上で心がけていることがあります。それは、できるだけ仕事を一人で抱え込まず、チームで共有することです。子供が急に体調を崩して休まざるを得ない時でも、他のメンバーが対応できるように、日頃から情報共有を徹底しています。
そして、夫の存在も私にとっては大きな支えです。私が出勤する日には、子供の保育園への送り迎えや入浴を担当してくれますし、時には夕食の準備もしてくれることもあります。夫の会社も育児に理解があり、応援してくれているからこそ、このような協力体制が築けているのだと思います。本当に感謝しかありません。
JA共済連では、育休制度が整っており、男性の育休取得も推進されるなど、子育てをしながら働きやすい環境が整備されています。また、時短勤務制度や在宅勤務制度なども活用できるため、それぞれのライフスタイルに合わせた働き方を選択することが可能です。私自身も、周囲の理解とサポート、そして制度の活用によって、仕事と育児の両立という充実した日々を送ることができています。

職場復帰後もフル回転。やりがいのあるプロジェクトにも参画
職場に復帰してからも、私はフル回転で業務に取り組んでいます。私が所属している事務企画部短期事務グループは、自動車共済や自賠責共済、そして火災共済といった、保障期間が比較的短い共済の事務を担当する部署です。ここでは、仕組改訂や事務改善など契約者・利用者にとってより良い共済や事務手続きの構築を検討したり、システム部門が構築した仕組みを、実際に事務手続きとして運用するためのマニュアル作成や改訂、そして都道府県本部に対して事務指導を行うための会議資料作成や打ち合わせなどを行っています。以前在籍していたシステム開発部はシステムを作る側でしたが、今はその仕組みを現場に伝える側に変わったということです。
この部署に来て特に印象的だったのは、育休に入る直前まで携わっていた農業者賠償責任共済「ファーマスト」の新設プロジェクトです。農業においては、生産から出荷、販売後まで、様々な賠償リスクが想定されますが、「ファーマスト」は、そうした農業者に共通する多様な賠償リスクを一体的に保障するという、全く新しい共済でした。本当に何もないゼロの状態から作り上げていくという初めての経験に、大変苦労しました。しかも、JA共済連の既存のシステムではなく、他社のシステムを一部共用するという案件であったため、そのシステムについても深く理解する必要がありました。まさに「0から1を作る」仕事でしたが、関係部署と協力しながら、なんとかリリースまで辿り着くことができ、大きな達成感を得られました。
この「ファーマスト」の経験があったからこそ、職場復帰後に参画した自賠責共同システム「One-JIBAI」の稼働対応プロジェクトも、無事にやり遂げることができました。「One-JIBAI」は、他の損害保険会社とともに、自動車損害賠償責任共済(保険)の引受・契約管理業務を行う業界全体の共同システムです。非常に大規模なプロジェクトであり、任される範囲も広く、また自賠責共済は私にとって初めて担当する分野であったため、一から勉強しながら取り組みました。
これらのプロジェクトは、いずれも組織内の様々な部署と連携しながら進めていきました。特に密に連携したのは、以前私が所属していたシステム部門の方々でした。システム構築をする上で生じる様々な課題に対して、一緒になって解決策を考え、取り組むことができました。
そのおかげもあってか、都道府県本部を通じて現場のJA職員から「画面の操作がしやすい」「手続きがスムーズにできる」といった、私が事務に関わったシステムに対するポジティブなフィードバックを聞けた時には、本当に嬉しかったです。このような声は、短期事務グループに異動してきて初めて聞くことができたものであり、私にとって仕事に対する最大の原動力となっています。
仕事と育児を両立していく上で、会社の理解とサポートは欠かせません。心強いのは、JA共済連には育児を支援する様々な制度が整っていることです。私も既にいくつかの制度を活用させてもらっています。
まずは、時差出勤制度です。私は自宅から勤務地まで距離があるため、朝の時間を有効活用しようと考え、通常よりも1時間繰り上げて午前8時から午後4時までを勤務時間としています。
また、在宅勤務制度も積極的に利用しています。在宅勤務の日は、私が子供の保育園の送り迎えや夕食の準備を担当しています。出勤時は通勤時間もあり勤務時間が長時間に及ぶため保育園の送り迎えが難しいですが、在宅勤務があることで千葉県に住んでいていても育児や家事の時間を確保することができています。こういったライフスタイルは在宅勤務制度がなければ、成り立っていなかっただろうと感じています。
他にも、JA共済連には時短勤務や時間外労働の免除、そして小学校6年生までの子供を持つ職員への支援制度など、様々な制度が用意されています。現時点ではこれらの制度は利用していませんが、夫の仕事の状況やライフスタイルの変化、そして子供の成長などに合わせて、今後活用していきたいと考えています。

全力で挑戦する人を必ず応援してくれる
育児と仕事の両立に追われる日々は慌ただしいものですが、気がつけば私もJA共済連の職員として入会して10年の月日が流れました。システム部門という、入会前は苦手意識を持っていた分野でさえ、経験を重ねるうちに面白さを感じるようになり、乗り越えてこられたことは大きな自信につながっています。不思議なことに、かつては敬遠していたシステムの専門用語や複雑な仕組みも、理解が深まるにつれて興味深く感じるようになりました。この事務・システム部門での経験は、現在の業務においても活かせていると感じています。
今後は、より現場の声が身近に感じられる仕事にも挑戦したいと考えています。10年間事務・システム部門に携わってきたからこそ、異なる分野にも積極的に挑み、新たな視点や経験を得たいという思いが強くなっています。
もちろん、今後も仕事と育児の両立は続きます。いかに効率的に仕事を進め、スケジュールを管理していくかは、引き続き重要な課題です。実は今も、出勤の高速バスの中では、その日の業務の段取りを再確認することを習慣にしています。「今日は何時までに何を終わらせる必要があるか」「優先順位の高い業務は何か」といったことを常に意識しています。そして、一人で抱え込まず、周囲と情報を共有し、助けを求めることも大切にしています。
「自分は仕事と育児を両立できるのだろうか」と不安に感じている学生の方もいらっしゃるかもしれません。大切なのは、ご自身の状況を夫や周囲の方々と率直に相談し、一人で悩みすぎないことです。また、良い意味で遠慮しすぎず、ご自身のライフプランを大切にしてほしいと思います。自分の気持ちを素直に打ち明けてみてください。JA共済連には、そうしたライフプランを尊重し、サポートしてくれる風土があると信じています。
学生の皆さんには、「自分は何が好きか」「何を大切にしたいか」という明確な軸を持って就職活動に取り組んでほしいと願っています。たとえ入会後に予想もしなかった困難な仕事に直面したとしても、その軸がきっと頑張り抜くための原動力になるはずです。JA共済連には、仕事やキャリアに対して高い意識を持つ職員が多く、そうした職員の活躍を支える制度や環境が整っています。全力で挑戦する人を必ず応援してくれる組織であることを、ぜひ知っておいてください。





