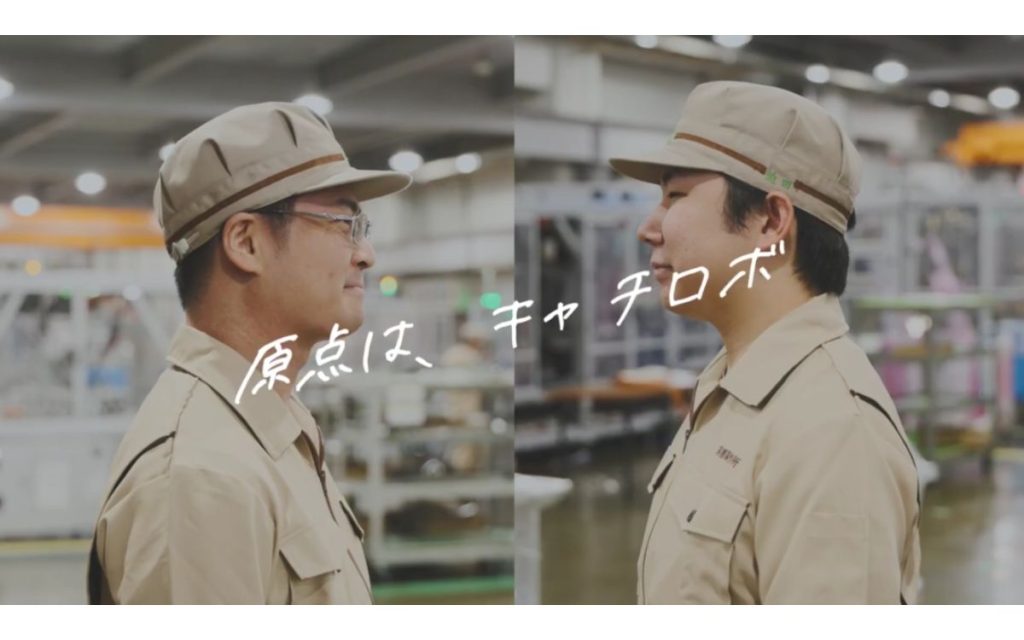集まれロボコニスト!若手エンジニア座談会!
集まれロボコニスト!若手エンジニア座談会!
このストーリーのポイント
- ロボットコンテストでの成功体験は?
- ロボットコンテストと実際の仕事の違いは?
- ロボットコンテストの経験は活かせてる?
- 京都製作所への入社の決め手は?
全国の学生が「つかむ」をテーマに自作ロボットでガチンコ勝負をする「キャチロボバトルコンテスト」。京都製作所はこの大会を長年後援し、熱い戦いを応援し続けてきました。学生時代にキャチロボバトルコンテストをはじめとする様々な「ロボットコンテスト」への挑戦経験を持ち、いま京都製作所で活躍する若手エンジニア6人が当時の悪戦苦闘の様子、現在の仕事について自由に語り合う座談会を開催しました。
株式会社京都製作所
【さんちゃん】
京都工芸繊維大学 卒
2023年入社/技術部 電気設計

【すーさん】
豊橋技術科学大学大学院 卒
2023年入社/技術部 電気設計

【ざっきー】
京都大学大学院 卒
2024年入社/開発部 機械設計

【エッセー】
室蘭工業大学 卒
2022年入社/技術部 機械設計

【アミロー】
和歌山工業高等専門学校 卒
2022年入社/開発部 機械設計

【ヨッシー】
京都工芸繊維大学 卒
2025年入社/技術部 機械設計

限られたルールの中で、モノづくりの技術と知識をぶつけ合う。アイデアとチームワークを駆使して難題に挑戦する。6人全員がそんなロボットコンテストに参加した「ロボコニスト」です。そしてロボットコンテストへの情熱そのままに、いま実用機械の開発に挑んでいる若手の「エンジニア」です。ざっくばらんに語り合う座談会で、さぁどんな熱い話が飛び出すのでしょうか。
ロボットコンテストで初めてつかんだ成功体験って、覚えてる?

【さんちゃん】 司会を務めます、さんちゃんです。まず自己紹介を兼ねて学生時代のロボットコンテスト歴、いまの所属などを簡単に教えてください。じゃあ、まずは僕からいきます。改めまして京都工芸繊維大学出身のさんちゃんです。キャチロボバトルコンテストでは、スナック菓子をつかむというテーマにRC多構造のロボットで挑戦しました。いまは機械を制御する電気設計をしています。
【すーさん】 僕は豊橋技術科学大学出身です。キャチロボには参加してませんが、大学ロボットコンテストでは走行距離40mという珍しいロボットを作りました。仕事はさんちゃんと同じ電気設計です。
【ざっきー】 京都大学出身のざっきーです。キャチロボには3回出場で、ロボットのアームを担当してました。最初の大会では4徹(4日連続の徹夜)したんですが、最後の大会は1徹で済むようになりました(笑)。現在は開発部で機械開発をしてます。
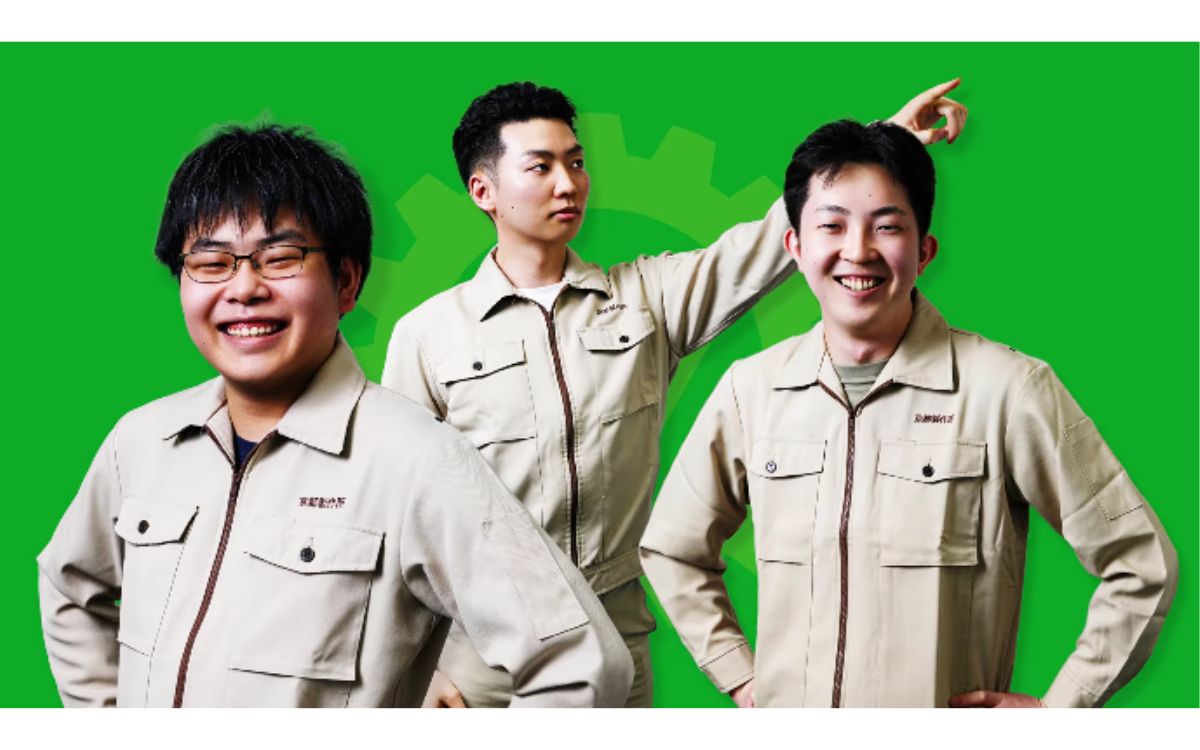
【さんちゃん】 そうそう、みんな何徹もしましたよね(笑)。では、エッセーさんお願いします。
【エッセー】 室蘭工業大学卒のエッセーです。キャチロボには合計4回出場しました。木のロボットからスタートし、最後は全自動で動くロボットを完成させました。技術部で機械設計をやってます。
【アミロー】 和歌山工業高専出身のアミローです。キャチロボはお菓子を3つ同時につかむという課題でした。他にペットボトルを投げたり、洗濯物を干したりするロボットコンテストにも挑戦。所属は開発部で機械設計に携わっています。
【ヨッシー】 京都工芸繊維大学卒で、今年4月に入社したヨッシーです。キャチロボではモーターの正転だけで、自動化をコンセプトとしたロボットを作りました。機械設計でホヤホヤの1年目です。
【さんちゃん】 みなさん、ありがとうございました。では最初のテーマに行きます。ロボットコンテストでの初めての成功体験って覚えてますか。まず、すーさん、どうでしょう?
【すーさん】 えーと、高専1年の冬に出場した関東地方の交流大会かな。そこで優勝したのが初の成功体験ですね。シンプルな機構をコンパクトに組み合わせたセオリー通りの機体が、セオリー通りに動きました。
【ヨッシー】 ロボットコンテストには6年出場してるんですが実は私、一回も勝ったことがないんですね。でもモーター1つの正転でカムを切り返して、ロボットがうまく動いた時は大歓喜でした。2徹の後だったんで、動画を撮影した直後に倒れました(笑)。小さな成功体験ですが、いまも忘れられなくて。
【アミロー】 ロボットコンテストは勝ち負けだけじゃなく、チャレンジできるところがいいよね!
【ざっきー】 自分も優勝とかないんですが、嬉しかったのはアームの精度を上げる減速機がうまくできたことですね。「サイクロイド減速機」っていうんですけど、中の歯車を10回くらいつくり直して、ようやく動いた時はもう最高。動いただけで大満足した記憶があります。
【さんちゃん】 プログラミングはやってましたが、僕は大学までロボットに触れたことがありませんでした。で、大学のサークルに入って「Lチカ」っていうLEDを基板から光らせる経験をしたのが衝撃でした。これまでプログラム上でディスプレイを見ていただけだったのが、実際の「モノ」として目の前で物理的に動いてる。その瞬間「これなら何でもできるやん!」と思いましたね。とにかく画面以外でモノが動いてるって感動が凄くて、ロボットづくりにのめり込むきっかけになりました。

学生のロボットづくり、いまの仕事のモノづり、その違いは?
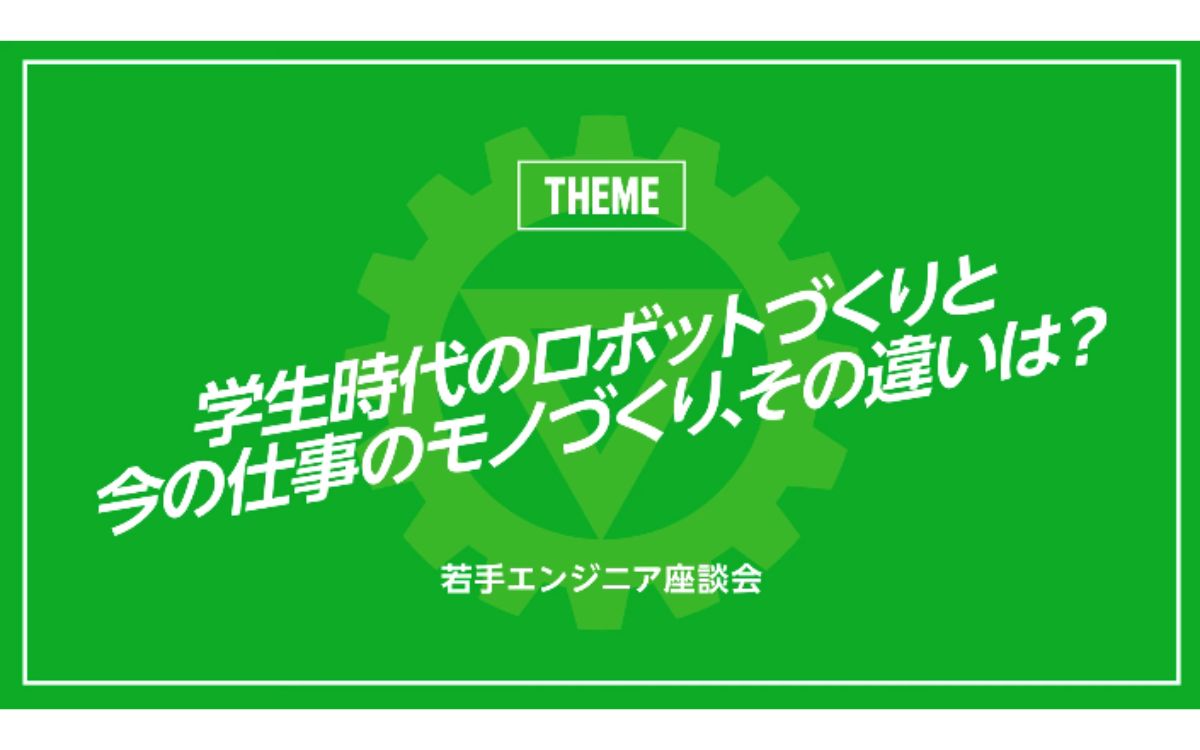
【さんちゃん】 それぞれ、ロボットコンテストに力を注いでたみたいですが、学生時代のロボットづくりと、いまの仕事のモノづくり、その違いは何だと思いますか。逆に繋がってるところもあれば教えてください。じゃあ、エッセーさんお願いします。
【エッセー】 そりゃ、お金と責任でしょ(笑)。学生の頃には使えなかったものが使えて、ロボットの値段も桁が違う。いろんなことに挑戦できるのは似ているけど、伴う責任はだいぶ違うよね。
【アミロー】 ロボットコンテストはある程度動けばいいやってところがあるけど、仕事じゃそうはいかない。お客様に納得いただけるまで、頑張って直し続ける。そこが違いますね。
【ざっきー】 ロボットコンテストだと、途中でナットが一つ落ちても「ま、いいか」てなってましたよね?
【全員】 そうそう、なってた!(爆笑)
【ざっきー】 でもお客様の機械のナットが落ちたら大問題なんで、そういった細かいところもしっかり配慮して設計しないといけないのが大きな違いかな。
【さんちゃん】 ロボットコンテストは制限時間の3分動けばいいやってノリだけど、仕事だと納品後何十年も使ってもらうことになるから、絶対にバグらない機械、絶対に壊れない機械をつくらないとダメですよね。
【アミロー】 そういえば寿命計算とかを真面目にやりだしたのも会社に入ってからだね。ロボットコンテストだとその辺に転がっているベアリングとか、古い部品を適当にくっつけたりしてたけど、仕事だとさすがにそうはいかないから。
【エッセー】 いい機械って何なのか、前に上司にこんなことをいわれたことがあります。いい機械は評価されにくい、うちの包装機械は使いやすくて壊れないのが当たり前だから評価されにくいって。「使いやすさ」は他社の機械と比べて初めて分かることで、1台だけを見て判断しにくい。要はお客様が使いやすさなんて気にも留めず、ずっと問題なく動くのが「いい機械」なんだって。
【さんちゃん】 なるほど、いい話ですね。ざっきー、何かありますか?
【ざっきー】 学生時代は部品を削るにしても、3Dプリンタを使うにしても、簡単なものしかできなかったけど、いまは「これ削れるの?」みたいな、とんでもない形状の部品でも削れます。もちろんコストは考えるけど、1個1万円の部品が何十個も出てくると、うおおーっと思っちゃいますね(笑)。動かせるお金の違いはすごく感じます。
【エッセー】 それだけお金もかかるけど、いろいろ挑戦させてくれる。やってみたいことができる。いい会社だよね(笑)。
ロボットコンテスト経験が仕事に役立ってる場面、いっぱいあるよね。

【さんちゃん】 では次のテーマです。ロボットコンテストで鍛えた技術や考え方が、いまの仕事の中で「使えてる、役立ってる」って思う瞬間はありますか。
【アミロー】 僕は割と挑戦的な機械をつくることが多くて、「どこまでいけるんだろう?」っていうのを試す場面がよくあります。そんな時は「とりあえずやってみて感覚を掴んでいこう」ってなるけど、いつも「これロボットコンテストと一緒だな」って思いますよ。大会ルールが発表されたら、どんなことができるか、ひたすらつくって試して、つくって試して…。そんな中で「これならいける!」を見出す。仕事も同じ感じでやってます。
【エッセー】 確かに。同じような機械でもお客様によって要望が違うのは、大会によってルールが違うのと似てるね。
【さんちゃん】 僕の場合、ロボットコンテストはバグとの戦いでした。ちょっと動かしたらバグがでて、それ修正したら別のバグが起きて…。プログラムを書いてる時間は4割くらいで、残り6割はずっとバグとの格闘。これ、いまの仕事とも似てるんです。うちは毎回違う機械をつくるから、当然プログラムも全部違いますよね。だからめちゃくちゃバグが出る。どう取り除くかっていうノウハウとか根気強さは、ロボットコンテストで鍛えられたなって感じてます。
【エッセー】 で、実際はどう取り除くの?
【さんちゃん】 とりあえず動かしてログを取って、そのログの怪しいところをさらにログを取って、原因見つけたらとりあえず潰して、潰したことで他のところに影響が出ていないかをまたテストして…。それをグルグル何百回、何千回やっていくことで、最終的にバグがほとんどない機械に仕上げます。ちなみに同じ電気設計のすーさんは?
【すーさん】 そうですね、バグ対策はさんちゃんと同じ。トラブルシューティングも同じかな。ハード面でも光電センサーとか、エアシリンダーとか、オートスイッチなんかは学生時代に使ってたツールとだいたい一緒。ロボットコンテストで散々、試行錯誤したベースがあるのは、トラブルシューティングにも役立ってると実感してます。
この機会に、みんなが「京都製作所」を選んだ理由を知りたい!
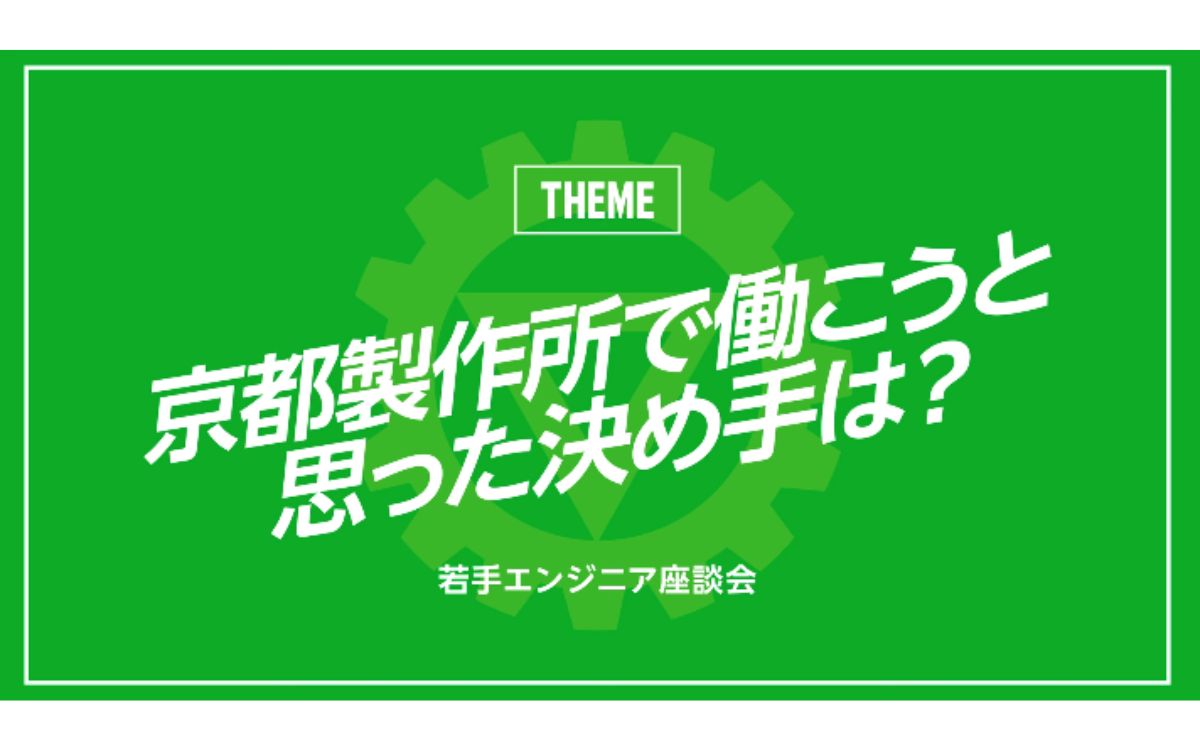
次のテーマは「京都製作所で働こうと思った決め手」。ふだん、あんまりこういう話をしないので、この機会にぜひ聞きたいですね。じゃあまずは入社したてのヨッシー、ぶっちゃけ決め手は何だった?
【ヨッシー】 私はキャチロボに選手として4回出て、運営でも1回関わってるんですが、そこでの京都製作所の社員さんの印象が大きかったですね。選手の時も気さくに話しかけてくれたし、何より社員さん同士が仲良くて、人間関係がいいんだろうなって感じました。あとは「生涯、エンジニア」っていうキャッチコピー!これ、いいですよね。実は父親もエンジニアなんですが、「管理職になってから設計させてもらえない」って唸ってるんですよ。だから私は「生涯エンジニア」で行きたいと思ってここに決めました。
【さんちゃん】 うちでは課長・次長クラスも、いつまでも設計してますもんね(笑)。ざっきーは?
【ざっきー】 キャチロボにもめっちゃ出たんですけど、その時の工場見学が決め手の一つですね。とにかく好きな機械ばっかりで、自分もつくりたいと思ったのが一番の理由。あと、親が転勤族でめちゃくちゃ引っ越してて、京都本社が開発本拠の京都製作所なら、転勤の心配もなさそうでしたし。
【エッセー】 僕も見学した機械が、どれもすごく速くて正確でかっこよくて、これつくってみたいなと思ったのがまず一つ。あとは工場がキレイだったんですよね。勝手なイメージですけど、モノづくりの工場って、油や金属屑で汚れてそうじゃないですか。それが切粉一つ落ちていないし、床も輝いてるし。部品をつくってるとは思えないキレイさで、いいなぁと思いましたね。
【アミロー】 学校の部室、切粉落ちまくり、散らかりまくりでしたよね(笑) 。僕も床に顔が映るほどのキレイさにはびっくりしました。それと設計室と組立場所が同じ建物の中にあるのも魅力でした。自分が設計した機械が1階で組み立てられて、実物が動くのをスグ見られるし、トラブルがあっても徒歩1分30秒で行けるし。この近さってロボットコンテストやってたころと同じですよね。実際、いま仕事してて画面見て悩んじゃうとかがあるんですけど、工場で実物を見ると何か閃いたり、気分転換になったり。いい環境ですよね。
【すーさん】 トラブルシューティングの時に現物があると、全然効率が違いますもんね。いまは遠いところでもPCが繋がってれば仕事ができたりするけど、やっぱり現物が近くにあるのはいいですよね。
【アミロー】 自分が設計した機械を組み立ててもらって動いた時はやっぱり一安心しますね。我が子みたいに愛着が湧いて、めちゃめちゃ可愛いし。
【ヨッシー】 自分で産んだ感、ありますよね。お腹を痛めて、苦しんで(笑)。
【さんちゃん】 ちょっと脱線気味なんで、話を入社動機に戻しますね。すーさん、どうですか?
【すーさん】 高専と大学の両方でいろんなロボットコンテストに出場したんですが、キャチロボには出たことがなくて、京都製作所を知ったのは会社説明会でした。で、面白そうだと思ってインターンシップに参加して、工場も見学して。そんな中で人事の人から仕事内容を聞いて「ロボットコンテストと一緒だ!」と思ったんですよね。ここなら学生時代の続きができる。入社して「思ってた仕事と違う」ってミスマッチはまずなさそう。そう思えたのが決め手ですね。
【さんちゃん】 入社動機、僕もよく似てます。ロボットコンテストって毎年ルールが違いますよね。だから毎回、新しい課題に挑戦していくのが楽しくて。工場見学で同じ機械がまったくないのを見て「ロボットコンテストと同じやん!」って感じたんです。お客様に合わせて一台一台、全然違うモノをつくる。設計から出荷までだいたい半年以内というスピード。そんな話を聞いて、ここならいろんな機械を楽しめる、挑戦のチャンスが多いと思って入社を決めました。 あっ、最後にいまロボットコンテストに夢中になってる学生さんに何かメッセージを伝えませんか。

【エッセー】 えーと、「いまロボットコンテストをやってること、絶対無駄にはならないから、そのままどんどん突き進め!」ですね。学生時代にしかできないことがいっぱいあるし、いまの時間を大切にしてほしいなって思います。こないだまで学生だったヨッシーはどう?
【ヨッシー】 いま仕事でつくってる機械も、動くとやっばり嬉しいし、達成感もめっちゃあるし。そのいちばん底にあるのって「ロボットが好き」って感情だと思うんです。だからいまの「好き!」っていう感情を大事にして欲しいです。
【すーさん】 ロボットコンテストで試行錯誤の経験をいっぱいしてください。働き始めて知らない分野にどうアプローチするかも結局、試行錯誤なんですよね。いまの試行錯誤、社会人になって活きてきますよ!
【エッセー】 学生のうちにいろいろ失敗しておけば、引き出しが増えます。働き始めると、その引き出しが役に立つことがたくさんありますよ。
【さんちゃん】 僕は、いまソフトや回路をやってる人もハードに興味を持って、逆にハードをやってる人もソフトに興味を持ってほしいと思います。いざ仕事で設計ってなった時、例えばプログラムってこういう風に動くからここにセンサーが要るよねって気づいたり、逆に電気設計者としてこういう風な構造になっているからこう動かして欲しいんだろうなって感じたりできるように。別の技術分野の人といちばん密に関われるのは、ロボットコンテストだと思いますから。
【アミロー】 さんちゃん、いいこというねぇ(笑)。それでいうと、ロボットコンテストでは他のチームがどんなアプローチをしてるかを見るのも大事。「その手があったか!」みたいなのがよくあるから。それも自分の引き出しを増やすチャンスですよ!
【さんちゃん】 ありがとうございました。今日はなんか、めちゃめちゃいい機会でしたね。また別のテーマで座談会、やりたいですよね。
【全員】 大賛成!
【エッセー】 次の座談会には、いまこれを見てる学生さんも参加してたりして。
【全員】 大歓迎!(笑)

※キャチロボバトルコンテスト(キャチロボ)とは
京都製作所がオフィシャルスポンサーを務めるキャチロボバトルコンテストは、マテリアルハンドリング技術 (マテハン)に特化した一般的なロボットコンテストと一線を画すユニークな大会です。京都工芸繊維大学、 立命館大学、大阪大学、同志社大学、大分大学、京都大学、九州大学のロボットサークルが実行委員となり、2025年で15回を迎えました。
「 機械は人間の手を超えられるか? 」 をテーマに、ワーク(ロボットが掴む対象物)のハンドリング(対象物をつかんで移動し指定の場所に収納する)を競うコンテストです。また、ワークがすべてお菓子なのも大きな特徴で、全て京都製作所のお客様の商品が使用されています。